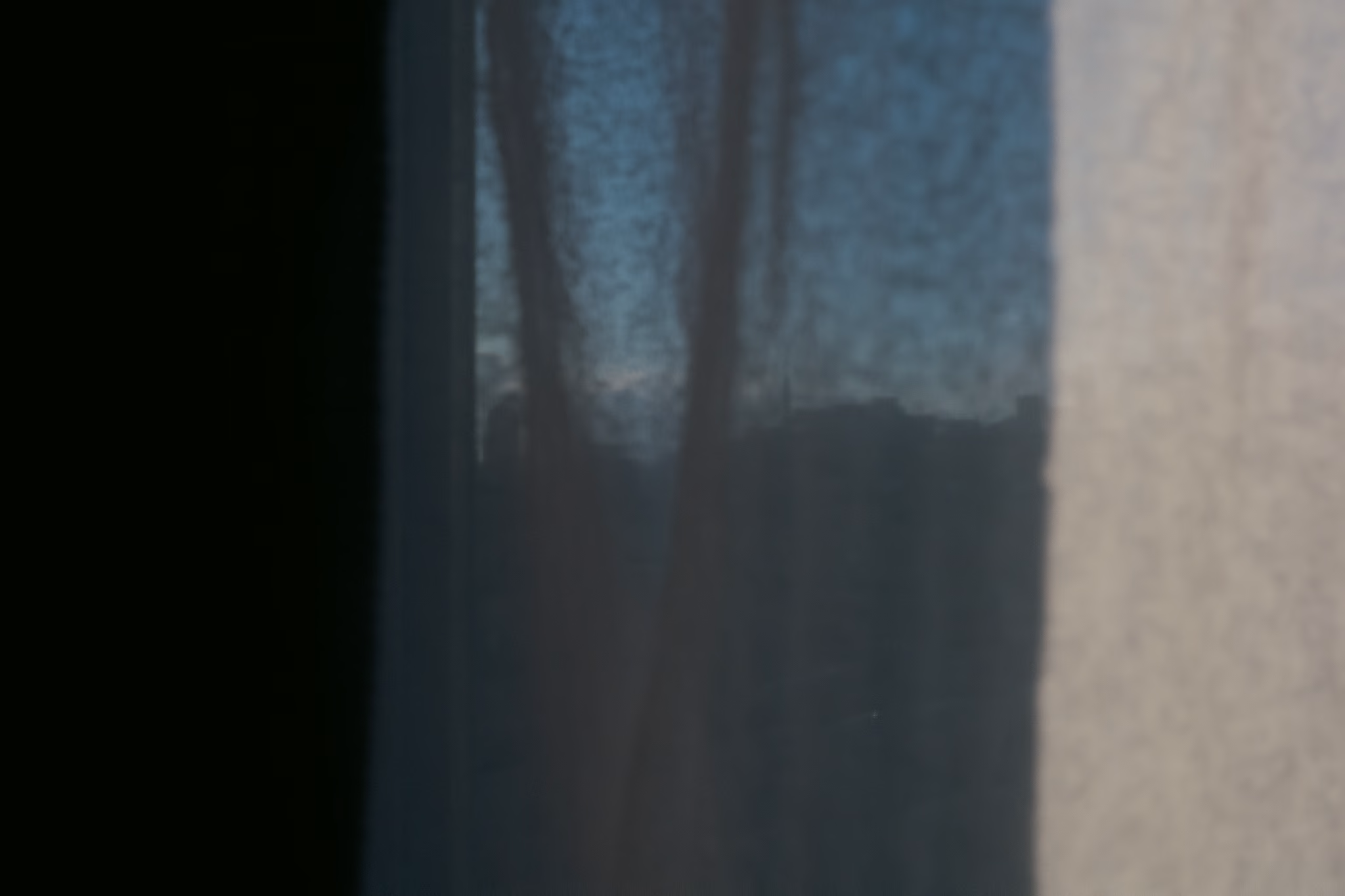1月15日の日記一覧
2026年1月15日
リトルKはこの頃、ママと保育園に行くといってぐずることが多い。歩いているとすぐに気分を取り直すのだが。保育園に送って、徒歩で出勤。
Kが用事があって外出するので、夕方、早めに帰宅してリトルKを迎えに行ったり、リモートで仕事したりする。その後、リトルKと一緒に夕食にシチューを作る。野菜を洗ったり、鍋に入れたりといったことを手伝ってくれる。しばらくやってると飽きて、YouTubeを見始めた。はじめしゃちょーの動画をこの頃は見はじめた。
寝かしつけした後、このところ読み進めていた東浩紀『平和と愚かさ』の続きを読み、読了。物事を考えるということのスケールの大きさがある。今後の世界情勢の変化を前に、ますます重要な内容になるだろうと思う。
昨日、画像をObsidianのエディタにペーストしたらR2にアップロードしてURLをMarkdown記法で貼ってくれるようにしたのだが、使っているプラグインにいくつか改善したいことがあったので、forkしたもの(kentaro/s3-image-uploader)を使うようにした。画像を貼ると同時に元のURLへのリンクにし、アップロードするパスを貼り付けたノートのパスと合わせるようにする変更を加えたもの。
新しいスマホにGRシリーズのカメラから取り込むアプリを入れようとして、GR Worldという新しいアプリが出ているのに気づいた。ファームウェアアップデートが必要。SDカード経由でしかできない。Windowsを起動してSDカードにファームウェアファイルを入れてカメラに移し、アップデートする。ネット経由でできるようになってほしいところ。
スマホでは家族写真とか記録用とかで普通に撮っているのだが、カメラを使ってそういうのを撮ろうとは思わない。モードが違う。カメラを使って撮るときは、自分の美的な価値観に準ずるもの、端的にいうと美しいと思える画像を作りたいと思う。以前はコンセプトを立ててしばらくそれに準ずる方向で撮ったりもしていたのだが、この頃はそういうことも考えなくなった。
共感されることもなく、アウトサイダーアートのように撮り続けているだけである。そのわりには量を撮り続けるみたいなことをしているわけでもないから、中途半端なわけだが。いずれにせよ、インスタに載せるみたいなことをしてもしかたがないし、出す場所もない。しかし、昨日から画像アップロード機能をつけたことで、とりあえずここに貼っておくことができるようになった。
そんなわけで、直近の写真からいくつか現像したものを貼っておく。
2025年1月15日
今日は一日、新規事業の戦略合宿。目標とアプローチの方針、ロードマップを描いていく。オーバービューを述べた後は時々口を挟みつつ、冒頭以外はメンバーに進めてもらった。事業に対する解像度が上がって、良いものになっていける実感を各人がそれぞれ持てるようにしていきたい。
夜は、クォーターに一度の日本CTO協会の理事・幹事懇親会。今年は内外ともに大きな動きがあれこれとありそう。新しく強力なメンバーも増えた。これからがますます楽しみである。
それにしても、ある種の場において自分の発揮し得る価値がどんどん目減りしていって、ほとんど残り滓のような感じだと思う。先行者メリットによってなにかしらのポジションに立てているというのはあるのだが、それは実績以上に自分をよく見せられているということで、良くも悪くもある。一方で、そのマジックももはやほぼ消滅したと思える。このままでは、残り滓も燃え尽きて終わっていくだろう。
自分がどうなろうと、それだけならそれはそれで別にどうでもいいといえばいえるのだが、そうもいってはいられない。なにかしら飛躍できるような結果を出さなければならないと思う。いくつかの方針は考えてはいるのだが、当然どれも困難かつ不確実な内容だ。しかしやりきらなければどうしようもないとも思う。
とはいえ、そんなに深刻にとらえたところで解決確率が上がるわけでもなく、むしろ悪い方向にいってしまうだけだろうとも思う。楽観的に思っておくことも必要だろう。というか、文章にするとやたら悲観的な感じに見えるが、気分としてはそういうわけでもない。単に現実を客観的にとらえたら普通にはそういう状況だろうということを記録しているだけである。
#日記 #1月15日
2023年1月15日
昨晩は「CQハムラジオ 2022年 12 月号」を読んだ。周波数別の特徴や実際が書かれているのが、とてもいい。こういうのは、一つずつ調べていくと時間がかかるからなあ。
ちょっと前に買った『手話でいこう―ろう者の言い分 聴者のホンネ』を読み始める。聴者の夫と、ろう者の妻という夫妻のそれぞれによるエッセイが掲載されている。半分ほど読んだところ。国内における、自分からは見えづらい異文化についての指南になるような本。亀井氏の『手話の世界を訪ねよう』も以前読んで、面白かったように記憶している。
Kとランチ。いい感じのピザ屋さん。ピザは美味しかったが、ランチとしてはちょっと高かったなあ。
壽 初春大歌舞伎のため、歌舞伎座へ。今日は第二部。今日の演目は、以下の通り。
- 壽恵方曽我
- 人間万事金世中
「壽恵方曽我」は、市川猿之助さん、松本幸四郎さんが曽我兄弟。工藤祐経を松本白鸚さん。歌舞伎らしい舞踊劇で、全員揃っての踊りと見得もカッコいい。白鸚さんの脇に控える市川染五郎さんが、前列に出てきての戦隊モノのような見得のしかたが、若々しく鮮烈。
「人間万事金世中」は、坂東彌十郎さん、中村扇雀さん、中村虎之介さんの親子のトリオでのやりとりが面白く、物語に精彩を与えていた。片岡孝太郎さんが「おくら」を演るのは無理があるように思われたが、シナは可愛らしい。それにしても虎之介さんは達者で、昨年秋の平成中村座での活躍も素晴らしかったし、今後の飛躍が楽しみな役者である。
大学院のゼミの新年会に出るために、品川へ。港南口の居酒屋さん。ここ半年ぐらい参加できないことが多かったのだが、あらためて研究もちゃんと進めていかないと。先生からも「もう1本はネタを作らないと」といわれたが、もちろんそのつもりでやっていかねばなるまい。
お茶しながら、無線やPremiere Proの解説動画を眺める。Premiere Proは、機能豊富な感じだが、使いこなせそうにないなあ。契約しているサブスクリプションにPremiere Rushがあったので使ってみたのだが、こちらはだいぶ不足している感じだった。どうしたものか。
帰宅して、週明けに備えて少し仕事を進めた。
今日のブックマーク
- 2020年、ポゴレリチ事件を感じる|寿すばる|note
- なぜ変化を起こすのが難しいのか? - 数年以上にわたって難しさに向き合い・考え取り組んできたこと / The reason why changing organization is so hard - What I thought and faced for more than several years - Speaker Deck
- アメリカ英語発音入門 完全ガイド 【超有料級】 - YouTube
- [syumaiさんはTwitterを使っています: 「たった116kbのWasmをロードすることで、ブラウザ上でLinuxのx86-64バイナリを動かせる時代になったらしい](https://t.co/DT5cArKAnV」 / Twitter https://twitter.com/__syumai/status/1614532426126221312?s=12&t=HDQd4Hju9UK2KKO2FyuoRg)
#日記 #1月15日
2022年1月15日
昨晩、寝る前に日本酒を1合ちょっと飲みながら本を読んでいたのだが、そのまま寝ついてしばらくしてから目が覚めて、しばらく寝付けなかった。そのせいもあってか、ぐっすり眠れた感じがせず、目覚ましが鳴っていたのを止めて、11時過ぎまで寝ていた。寝る間際に飲むとよくないなあ。
Kが出かけようというので、準備して上野へ。東京文化会館の精養軒で昼食。こちらには初めてきたが、いい感じの場所だなあ。例によってハヤシライスをいただく。
その後、国立博物館の東洋館で開催されている「イスラーム王朝とムスリムの世界」を見る。イスラームの、憶えきれない「〜朝」の変遷に沿った紹介と、カリグラフィや装飾品などのテーマごとの紹介と、大きく2パートに分かれた展示。分量はそれほど多くはないのだが、引き込まれる。当然イスラームも一枚岩ではなく、地域の文化との混成が多く見られる。特に、中国の色絵皿にアラビア文字の施されたものの不思議な感じに、心惹かれた。あらためてイスラームについて知りたくなり、カタログと合わせて『イスラムとは何か。』を買った。
公園口の建物の2階にあるカフェで抹茶と白玉のデザートをいただく。巨大な白玉が3つ入っていて、完全にトゥーマッチ。
帰りに新橋によって、お茶しながら神津朝夫『茶の湯の歴史』の続きを読む。例によって、通説を次々にひっくり返していく。文化史的観点による解釈ではなく、資料や茶の湯の実践そのものに基づく記述は、非常に説得的。面白い。
帰宅して、夕食をとりながら「ブラタモリ」を観る。今日は和歌山。秀忠が、要地であった紀州を頼宣に任せたということだったのだが、なぜ大阪ではなく和歌山だったのかというのはわからずじまい。大阪の方がよっぽど大事だったのではないかと思うのだが。ちょっとググってみた感じだと、よくわからない。
修論の続きを進める。とりあえず最後まで見直しをしたり、社会的・学術的意義や謝辞のパートを書いたりなど。現状で30ページほど。あとは実装についても書いたらどうかと先生から言われているので、明日はその部分をさっと書いてしまおう。なんだかんだで今日は遊んでばかりであまり進まなかった。
2021年1月15日
差し込みや、今日が期限の仕事などなど立て込む。しかし、やりたいことがたくさん出てきて、どう進めたものかという感じ。でも、そういうときが一番楽しくはあるなあ。
少し早めにもろもろ終わったので、18時以降は論文書き。第207回SE研究発表会に申し込んだので、いよいよちゃんとやらなければならない。というか、先日Y先生に共著をお願いした時点で自分だけのことではなくなっているので、ちゃんとやるつもりにはなっているのだけど。というわけで、今週末いっぱいでひとまず書いてお見せするという話をしたので、まずは文字を最後まで書く、つまり、ブラッシュアップできる前提のところまで持っていくつもりで、あとは書いていくだけ。
というか、いま書いている論文は、これを書いたからといって学位を取ることになんの関係もないのだが(正確には副テーマの2単位になるといいなとは思ってるというのはあるが、別にそのために論文を書く必要はない)、落合陽一さん的には博士課程で8本書いたということで、そんなんもう学位とかの問題じゃなくて書きたいことを書きまくってる感じでかっこいいし、自分もそうありたいと思って、なんかあれこれ考えずにやりたいことをできる限りやるということにした。趣味でやってることだから、効率考えてもしかたないし。
最近、論文書いたり仕事してたりで週に1〜2回しか夕食を作れていなくて、Kにやってもらっている。そのへんもうまくやれるようにしたいのだけどなあ。
2020年1月15日
福岡出張。朝、研修があり、冒頭で意義についてすこし話す。その後、いろいろ細々した仕事など。昼は紀文で鉄火丼。毎回きてる。午後は、新しく入社された方との面談や、今期の目標面談など。夜は、研究所のみんなで大濠公園の「橙」へ。とても旨い水炊きだったなあ。その後、天神にもどってバーでいっぱいやった後、ホテルに戻る。
2019年1月15日
面談の日。前向きにやっていく感じが醸成されてきており、いいなと思う。
終業後、個人的な生活面において、今年は20kg減量するという目標を立てているので、先週まで出張などあってできなかったで、今日からジムへ。1時間ちょい有酸素運動を行う。筋トレはちょっとぼちぼち。上半身はクライミングでできる面もあるだろうので、もちっと体幹的な感じでやるとよいのだろうなあ。
その後、カボットでワイン。ユドロ・バイエによるシャンボール・ミュジニーの村名V.V.の2014年。あれこれ国や地域を飲んできて、ようやくブルゴーニュの糸口をつかめたきがしている。めちゃめちゃ旨い。一方で、ローヌのシラー的なスパイシーさも感じる。ピノ・ノワールにも、かなりの幅があるのだなということを実感した。
いまから5年後は2024年、10年後は2029年というタイムスパンの中で、インターネットに関わるエンジニアがどういうふうになっていくのだろうかというのを考えている。その中で、人々それぞれと組織全体にとって、効用が最大化するにはどうしたらいいか。僕は少なくともこの3年ほどそれを考え続けているのだが、よりポジティブな形でアウトプットしていく必要があるだろうと感じる。
2017年1月15日
今日は2つ予定を入れていたのだが、さっそく寝過ごしてスタートが遅くなった。掃除、洗濯をしてでかける。 上野の国立西洋美術館。クラーナハ展を観る。  ザクセン選帝侯領で宮廷画家をつとめつつ、工房を率いて得意のモチーフを大量生産する事業家としての側面も持つ、ドイツにおけるルネサンスと宗教改革の只中にあった人物。やけに活き活きとした肖像画や、後年に量産した独特の抽象的なプロポーションを持つ裸体画が、やたら印象に残る。 クラーナハだけでなく、デューラーのような同時代の画家はもとより、ピカソやデュシャンによる継承、レイラ・パズーキによるインパクト大な「《正義の寓意》1537年による絵画コンペティション」なども楽しかった。 上野公園を抜けてルノアールで『昭和元禄落語心中』の続きを読み、読了。ご都合主義だったり、幽霊話に多くを依存しすぎていたりして興ざめなところがなくもないが、それはそれとして面白かった。 17時に鈴本演芸場へ行く。開場前から行列。開園時には満席になる。落語ブームなんだなあ。
ザクセン選帝侯領で宮廷画家をつとめつつ、工房を率いて得意のモチーフを大量生産する事業家としての側面も持つ、ドイツにおけるルネサンスと宗教改革の只中にあった人物。やけに活き活きとした肖像画や、後年に量産した独特の抽象的なプロポーションを持つ裸体画が、やたら印象に残る。 クラーナハだけでなく、デューラーのような同時代の画家はもとより、ピカソやデュシャンによる継承、レイラ・パズーキによるインパクト大な「《正義の寓意》1537年による絵画コンペティション」なども楽しかった。 上野公園を抜けてルノアールで『昭和元禄落語心中』の続きを読み、読了。ご都合主義だったり、幽霊話に多くを依存しすぎていたりして興ざめなところがなくもないが、それはそれとして面白かった。 17時に鈴本演芸場へ行く。開場前から行列。開園時には満席になる。落語ブームなんだなあ。
- 落語: 柳家ぐんま(平林)
- 奇術: ダーク広和
- 落語: 三遊亭歌奴(宮戸川)
- 落語: 柳家小傳次(たいこ腹)
- 音楽: のだゆき
- 落語: 春風亭百栄(新作)
- 落語: 桃月庵白酒(時そば)
- 漫才: ホームラン
- 落語: 古今亭文菊(締め込み)
- 紙切り: 林家楽一
- 落語: 柳家喬太郎(新作)
白酒さんは上手かったし、文菊さんが登場した時に、ぱっと空気が変わったのが印象的だったし、噺もよかったなあ。喬太郎さんは例によって大笑いさせてくれた。 「酒肴や 一」で軽く飲んで帰る。 
2016年1月15日
福岡出張、最終日。
I felt a solid response from interviews to engineers there and meeting with managers to adjust our eye level. On the other hand, I've been able to realize problem that is hard to solve. I need to involve all the key people to make us higher than now.
昼食はひらお。They have got popular year by year. Many people were making a longer line than the last time I visited. We tried to understand the algorithm of the arrangement of 天麩羅 to many people. It was really complicated, however they looked to easily do it well.
It's comparably easy to encourage only engineers to hustle. What really difficult is to pursue whole company toward the vision. To do so, I must spread my ability of involvement beyond distance of profession, belief, and capability. Our mission is to provide value to customers, which requires so called all-out fight.
I backed to Shibuya around at 9:00 p.m., and went to ひで to have おでん, and found it absolutely great place. I have known it before long years, but I've been there for the first time, today. 円山町という土地柄、花街感があって敷居が高い感じなのだけど、they welcome us frankly and felt comfortable, and おでんがとても美味しかった。
多言語が使える作家でも、作品を書くとなるとたいていはほぼひとつの言語だけで書くことがおおい。I feel it's too conservative, although I guess it's because of marketing, だけど表現者としてはもっと自由に書いてもいいように思う。そういう作品を読みたいなあ。そのためにもいろんな言語を読めるようにならないと。