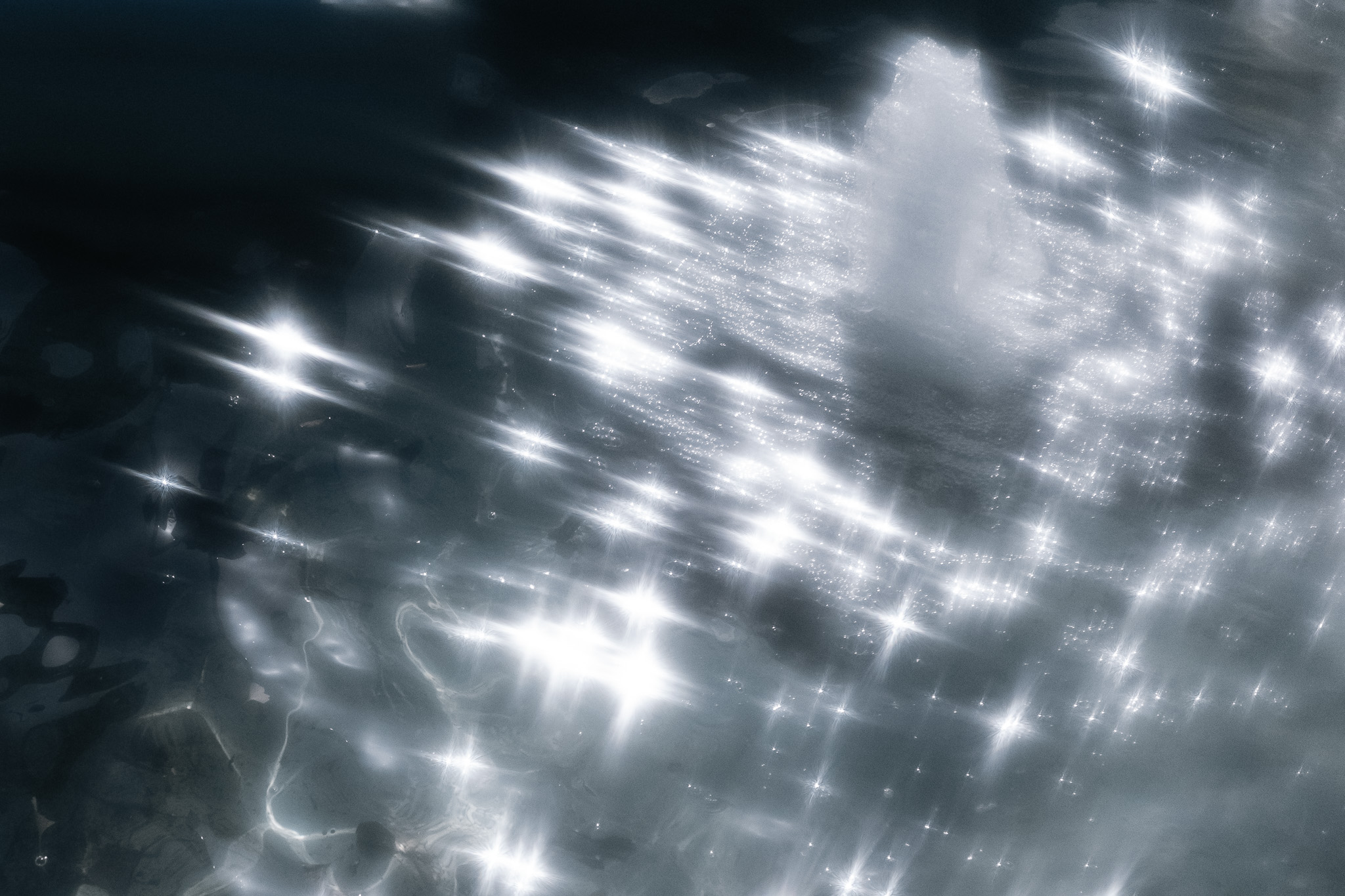1月18日の日記一覧
2026年1月18日
本を読んで遅くまで起きていたのだが、わりと早い時間に目が覚めてしまって、そのまま起き出す。
リトルKと公園へ散歩。Kもいくといっていたのだが、リトルKが「ママは仕事だからパパといく」というので、Kは家の用事。木の実を拾ったり、朽木を割ったりする。あいかわらず虫はほとんど見つけられない。毛虫や、カマキリやカイガラムシの卵鞘を探す。歩きながら、写真を撮ったりもするが、いまいち気分が乗らない感じ。ぐるっと一周まわった後、喫茶店で休憩。リトルKはりんごジュースとワッフル。
帰宅して、しばらく昼寝。歩いているうちから眠くてしかたがなかった。しかし明るいとうまく眠れず、うとうとして過ごす。 団地ラジオで佐伯ポインティ氏が言及していた「プルリブス」を観始める。一風変わったゾンビものか?と思いきや、意外な展開に。しかし、Amazonプライムビデオだと追加でApple TVのサブスクをしないと1話だけしか観られず、ドラマを観るのに時間を割くのは難しいし、かえって安堵した。団地ラジオはすごく面白いのだが、社会的な状況や文脈との接続がストレートなところにちょっと違和感を覚える。
お世話になっている写真家さんのアシスタントM氏が独立するので「追いコン」が開かれるということで、三宿まで。たくさんの人々が集まっていて、人徳を感じる。Kが、昨日の展覧会のキュレーターの方に夫がよかったといってましたというと、どこが面白かったかきかれたので説明をし始めたら、全然「芯を食ってない」感じになってしまってよくなかった。もっと「素直」な感想を述べるべきだったなあ。三宿交差点から少し離れたところにあるうどん屋さんで夕食をとって帰宅。
リトルKは、マグフォーマーで遊び始めてから造形感覚が発達してきている感じがある。ブロックも前よりあれこれ作れるようになってきた。このところ、Kや私が注意すると、相手のいっていることをそのままオウム返しにすることを繰り返す行動が見られる。客観的に状況を眺めている感じ。比喩や記憶の想起もよく見られるようになってきて、また少しモードが変わってきている感じがある。
志村貴子『放浪息子』を読み始める。連載時に途中まで読んでいたけど、途中までで止まっていたもの。志村貴子氏の漫画を読む感じから遠くはなれてしまって久しいのだが、Kindleセールで買ったところからまた戻ってきつつある。やっぱり素晴らしく面白い。この10年ぐらい読めてなかったものも含めて、あらためて読んでいきたい。
とりあえず今日撮ったもののうちからいくつか現像する。彩度を極端に低くしたピクトリアリズム的なイメージの方向性を探る。
2025年1月18日
昨晩は、日記を書いた後、結局5時頃までAIエージェントとたわむれていた。今日は昼過ぎに起きた。久々によく寝た感じがする。昨日から家族が実家へ帰っているので、のんびりしている。
昼食をとりに出かける。お茶しながら新聞を読んだり、Foremというオンラインフォーラムを作れるOSSについて調べたり、GitPodcastで遊んだりする。
自分用AIエージェントをWebアプリとして作っていたのだが、入り口はふだん触るものがやっぱりいいよなあと思って、Discordをメインにすることにした。バックエンドはn8nを使う。Raspberry Pi上で動かす。n8nのワークフローを外部からも編集できるようngrok経由でアクセスできるようにしたり、ngrokの再起動後にはURLが変わるので新しいURLをDiscordに通知するようにしたり。さらに、それらをsystemdのサービスとして自動起動できるようにもした。久々に自宅サーバを構築した。楽しい。
n8nのみで動くワークフローとして、まずは朝の挨拶をしてくれるものを作った。ついでに、この日記の内容を要約してXにポストするのも作ってみた。さらに、Discordのメッセージを起点に動くワークフローを作るため、ユーザからのリプライと返信を受け取ってn8nにわたし、処理結果をユーザへの返信として返す簡単なボットを書いた。発言をパースしてコマンド抽出したりはするが、ほぼ受け渡しをするだけ。具体的な処理は、n8n上のみで書くようにしてみる。
そんなことをしているうちに夜もふけてきてお腹が空いてきたのでコンビニに寄ると、「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 クリームシチュー味」なるものがあったので買ってみた。久しぶりにカップ焼きそばを食べた。その後、部屋の片付けをしたり、靴を洗ったりする。
さらにコード書きとn8nいじりの続き。あれこれハマったりしていたのだが、n8nについてだいぶわかってきた。ややとっつきにくい感じがあるが、使ってみるとこれは便利だなあ。
家でひとりなのをいいことに、ずっとAIエージェントとたわむれたり、自分用のものを作ろうとしてみたりした1日。
#日記 #1月18日
2023年1月18日
昨日、張り切りすぎたせいで疲れ気味。眼鏡が、度を以前のものと同じにしてもらったのだが、左目がちょっと合わない感じがして、目がとても疲れてしまう。慣れるまで我慢するしかない。
ミーティングや1on1などであれこれ話していて、先行き的なところをまたアップデートして行かないとなあと思ったりした。
千葉雅也さんの「「男の料理」的追求へと向かわないこと」という記事を読んで、長年思っていたことが言語化された感じがする。「男の料理」的なものが悪いとは思わないが、料理そのものについては、自分ではやらない。しかし、趣味的な話についてはついそういう追求のしかたをしてしまって、自縄自爆になることがよくある。もっと気楽に「切断」していかないと。
という話をTwitterに書いていたのだが、別件でK氏がある動画編集ソフトの無料版を勧めてくれたのに対して、使っているうちに有料版にしたくなるだろうから迷っていると回答したら、それこそ「男の料理」的な態度ではないかといわれて、まさにその通りであると虚を突かれ他ということがあった。「男の料理」的態度から逃れるのは、かくも難しいことである。
しかし、千葉さんが書いているような、仕事や研究的なこと、あるいは料理についても、自分は「男の料理」的な態度をいい感じに回避できているんじゃないかと思う。必要に迫られてやっていることに関しては、そういう勘所があるんだと思う。一方で、趣味的なことについては先述の通りで、そうなると趣味そのものを回避するか、趣味をもっと軽やかにするかということになろう。
『英語のハノン 中級』の3周目を終えた。といっても、通勤時に流しながらボソボソいっているだけで、1つのトラックをすんなりいえるまで繰り返すようなことはしていない。なので、苦手な文は相変わらず苦手なままなのだけど。でも、最初より少しはマシになっているようにも思える。このままあと2周ぐらい回してから、上級編をやるようにしようかなあ。
WebAssemblyについて、「WasmでJavaScriptを動かす意義 - id:anatooのブログ」を読んであらためて興味を持ったので、ElixirからWasmランタイムを使えるライブラリを触ってみる。うまく動かなくて、四苦八苦。ついつい夜中までやってしまう。
今日のブックマーク
- 1アマ国家試験、工学科目の挫折を防ぐためのポイント:受験勉強を始める前にやっておきたいこと - YouTube
- 【無線】デジコミで遠くと交信するには?アンテナごとの距離目安と山越え交信を可能にする方法 デジタル小電力コミュニティ無線 DJ PV1D - YouTube
- 【無線】LCRがなぜか復調しない… Sは振れるのに音声が聞こえてこないときの原因と解決法 実験映像と共に解説 デジタル小電力コミュニティ無線 DJ-PV1D - YouTube
- 文章作成の頼れるアシスタント、AI搭載のDeepL Writeが新登場
- WasmでJavaScriptを動かす意義 - id:anatooのブログ
- ARDUINO FOR HAM RADIO :: RTTY
#日記 #1月18日
2022年1月18日
朝、起きたら起きたら起きたら10時を過ぎていた。昨日もなかなか起きられなかったので目覚ましが無効になっているのかと思ったのだが、設定はちゃんとしている。気付かないうちに止めているのだろうか。危険である。そんなわけで、30分の研究タイムはなし。その後、評価関連の作業。いつも、どうするかかなり考え込んだのちに、これが本人にとっても会社にとってもベストという結果を出すことを心がけてはいる。人々が自らの成長の糧にしてくれるとよいが。
遅ればせながらWEB+DB PRESSの最新号を読んでいたら、次号予告に我々の特集が出ていた。半年がかりのプロジェクトだったが、いよいよである。ゲラ前の著者校正の段階にあり、製品に向けて最後のブラッシュアップをしているところ。タスクが少しあったので、Centeredでフローに入って40分ほどで完了。
Kが注文したホタテが届いたのを調理してくれた。特に焼いたホタテの、なんか入れてるのかと思えるほどの旨味がすごい。驚く。「常きげん」を軽く飲みながらの夕食。そんなに飲んでないのに体にくるなあと思っていたのだが、これは原酒なのであった。そんなわけで、少し寝る。
『美学のプラクティス』の続きを読む。極めて面白い本。整理が明快で、主張もシャープ。ソーシャリー・エンゲージド・アートが、むしろ美的なものとしてのアートを危険視してそこから脱するというのであれば、それはそれで放っておいたらよいのではないかという気もするし、個人的にはそれでもいい気もしたりするのだが、アートの形式的な分析をそれでも必要とするというのはどういうところから来るのだろうかという気もした。
Wordle - A daily word gameという単語ゲームがしばらく前から周囲で取り組まれている。僕も4日ほど前からやるようになったのが、けっこう面白い。頭の体操という感じ。
ひょんなことからRIP SLYMEの動画を観ることになったのだが、その過程でちょっと前に怪文書的な揉め事があったのを行き当たった。RIP SLYMEについて、シングル曲をいくつか知っているだけという感じで全然ちゃんと聞いていないのだが、聞いたことのある曲はどれもPV込みで素晴らしいものばかりだという記憶があるので、寂しい思いを少し感じた。
まだ修論も終わったわけではないが、次のステップや次の研究テーマなどにもそろそろ取りかかっていく必要がある。次の研究テーマの方はアウトプットのターゲットを決めてないのでちょっとぼーっとしてしまっているから、ちゃんと決めていかねば。
2021年1月18日
土日に習慣実行のリズムが崩れてしまったので、意識的に取り戻していく。しかし、なんだかんだでやることがあれこれあって、いくつかこなせないまま時間が過ぎてしまう。また、夜は論文書きを始めたら思いのほか興がのったこともあり、ひたすら書いていて他のことができなかったなあ。
というわけで、終業後は論文書き。週末は全然乗れなかったのだが、落合陽一さんが、研究は生き方だけど論文はゲームとして攻略するべきものだという感じのことをおっしゃっていたのを思い出して、マインドセットを切り替えたら、書くスピードが少しあがってきた。文章を書くことに対して、なんというか自己表現的な感じで向き合ってしまうのだが、論文を書くのはそういうのとは違って外部に基準のあることだから、自分のやり方を捨ててやるべきことをやるだけだなと思って、ある意味気が楽になった。そう思って書くと、とりあえず書けるだけ書こうという感じになって、1時頃までわーっと書いた結果、「おわりに」まで文字をとりあえず書くことができた。
書いてみて、思いのほか文章がどんどん崩れていって、整合性が全然取れなくなってきているのがわかるのだけどなかなか体勢を立て直すのが難しい。しかしまあ、いったんは最後まで終わらせて、ブラッシュアップは何周もする過程でやろうと気を取り直してやっていった。性が進むにつれて雑になって、書くべきことも書き漏らしていたり、もっとちゃんと述べるべきことを述べてなかったりしている感じもするのだけど、それもあとから回していく過程でよくしていけばよいだろう。2月8日が締め切りなのでそれまで時間もあるし。「はー、しかしはやく自分もジャーナルに採録されるような論文を書きたい!」という気も強くする。
2020年1月18日
ワタリウム美術館へ「フィリップ・パレーノ展、オブジェが語り始めると、」を観に行く。人間ならざるものの語り、あるいはなんらかの表出、それらとのコミュニケーションに興味を抱いている。本展は、アート的な面白みはあるものの「オブジェの語り」としてのしかけは単純で、そういう意味ではイマイチ。まあ、目的が違うのだろうから、だからといっていいとかわるいとかいうことではないのだが。
そこから、南青山のMazajに寄ったのち、void+で保井智貴さん、NANZUKAで鬼海弘雄さん、CASE TOKYOで百々俊二さんの作品を観る。
帰宅して、タグボートの社長さんによる『教養としてのアート 投資としてのアート』を読む。現代アートのビジネス的な事情については他にもっといい本があると思うが、アート作品を投資として買うに際しての「鉄則」については、効果的なアドバイスがされていると感じた。ただまあ、たいていのひとはアートで投資としてもうけることはほぼ無理だと思われるので、好きにやったらいいのではないかとも思う。
最近、ちょっと目先を変えた、自分の趣味に基づくビジネスのプランを考えてみるということをしていて、たとえばシーシャ屋とかアートギャラリーとかについて考えている。シーシャ屋はかなり原価制約の強いビジネスなので、あんまり旨味がなさそう。アートギャラリーは、不動産・投資・タレント事務所・企画・営業・社交などなど、総合的なビジネスであり、面白みはある。しかし、たとえば不動産を持ってるとか、他のビジネスでまわっている物理的な拠点があるとか、そういう条件がまずは必要そう。
2019年1月18日
昨晩、M氏と話したことをふりかえって、自分のやるべきことを見定めた。ありがたい。
『Design Systems ―デジタルプロダクトのためのデザインシステム実践ガイド』、『ハーバードの人生が変わる東洋哲学: 悩めるエリートを熱狂させた超人気講義 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫)』を買ったので、それぞれ読み始める。とてもよい。その後、誕生日イベントで飲んでからの、Ninty Plusでカルフォルニアのピノ・ノワール飲み比べ。レベル高い。
2017年1月18日
福岡からきてるメンバーとあれこれ仕込み。大変そうだけど、やれたらすごい。がんばろう。
終業後、会社の人々と飲み。「速」がどうのとかいいまくっていた。
2016年1月18日
Woke up at 8:15 a.m. and practiced meditation for fifteen minutes. I hardly concentrated on it, though. Random thoughts, that is said "monkey mind", disturbed me from being mindful.
Today, I wrapped up the results of interviews of engineers and got some insight from them. Having solved one issue, another one emerged. Endless step to proceed the organization toward the brilliant future.
I, however, must start committing the essential job for me, which piled up while I've been into obligatory and pressing "tasks". It's actually a phony when we feel that we do hard work with such tasks. Such tasks are definitely important, but what we really focus on is always other thing. We must avoid being satisfied with the feeling that we work hard on what we can do.
Whenever I attend at meetings with executives, I always feel like I'm inferior than them. I need to be able to make efficient proposal to them.
Bought two bottles of sake. The one, Suiryu, is full of umami and the other, Tamagawa, is fresh and rich. Tamagawa is brewed by a man from England. He is the first man who became Touji that is responsible to the taste of sake. I found recently he did really good job. It was exciting!
It was absolutely disgusting that certain people exploited the public airwave to force their employees to apologize to them and the TV station permitted such an offer from someone in the trouble. There was no true audience. It was just to meet the private demand of those people. I think they're crazy as public figures. I hate TV.