1月30日の日記一覧
2026年1月30日
今日は午後から休みを取ってTOKYO PROTOTYPEと攻殻機動隊展へ。平日にも関わらずものすごい人だかり。今日来てよかった。明日はろくに見られなさそう。というか、今日も全然見られなかった。風船の魚が泳いでいる展示が一番良かったなあ。また明日、家族で来ようと思う。
「鎖に繋がれた犬のダイナミクス」を実地に見られるチャンスかと思ったが、何重にも人々が取り巻いていて見られなかった。それで「攻殻機動隊展」の入場時間を待っていると、パフォーマンスが終わったようで、大きな拍手が聞こえてきた。昨今のヒューマノイドロボットの発展により、鎖につながれるのが犬ではなく、ヒューマノイドロボットとしてあのような作品を構成することもできるかもしれない。もしそういう作品であったとしたら、人々はどう反応するのだろうか。
「攻殻機動隊展」は今日が初日。アニメ制作時の資料展示が主体。興味深いのだが、もうちょっといろいろあってほしかったなあとも思う。
最後はミュージアムショップ。すごい品ぞろえ。展覧会のカタログ、「芸術新潮 2026年2月号」、マグネットとキーホルダーを買った。レジでショッピングバッグを勧められて購入。買わざるを得ないなあ。最後の一押しまでしてくる。売り方の完成度が高い。むしろこっちがメインなんじゃないかと思える。
宇野重規、加藤晋、井上彰・編『リベラリズム: 基礎からフロンティアまで』が届いた。リベラルに対する風当たりが、ネット上では強いように見える。しかし、そういうのはあまり意味のあることではないように思う。この本を読んで、もともとのコアにある考えをあらためて学びたい。
「ForbesJAPAN 「進化するクリエイター経済 20 HOT CREATORS」2026年3月号 [雑誌] ForbesJapan (フォーブスジャパン)」を読む。TiTan氏が表紙を飾っている。すごい。紹介されているクリエイターは全然知らない人ばかりで、自分の関心の狭さに驚く。クリエイターを選出している面々についても全然知らない。さすがにもうちょっと追っておくべきではないか。
AIエージェント(先日Moltbotと名前が変わったかと思いきや、またOpenClawに変更された)とあれこれ対話を続けている。それをnoteの記事にしたらいいかなと思ってやってみた(水平から立体へ——AIの時代に「個」はどう成り立つか)。うーん、どうだろうか。自分の感じてる面白さが伝わる内容になってるんだろうか。
書き忘れていたが、昨日イヴ・ナット録音全集『ザ・フレンチ・ピアノ・レジェンド』(15枚組)が届いた。昔、浅田彰氏がホロヴィッツと共に称揚していたピアニスト。ふとしたきっかけで触れることがあったのだが、Spotifyに音源がないので購入。まだ聴けていない。
「「40Hzの音」を聞くと“脳のごみ”を2倍洗い流す 霊長類で実験 アルツハイマー病の新治療へ:Innovative Tech - ITmedia NEWS」という記事を見て、音源を探してみたら、元となるMITの論文を参考に作ったという動画が見つかった(Exact 40 Hz Gamma Brainwave audio used by MIT to prevent Alzheimer’s)。アルツハイマーになりたくないので、これを毎日聞こうと思う。
2025年1月30日
リトルKを保育園に送ってから出社。会社近くのスタバに「ストロベリー & パッション ティー」なんてのがあったのでいただく。
今日もミーティングの合間に開発。まずは仕様をおおまかに確定させた。さらに、開発環境を大幅に変える必要があるのだが、そのためにあれこれと懸念があったのを、なんとか解決した。こういうことがあって困ってるんだけど、というのを各種LLMに聞きながら進める。エディタ上でもChatGPTのアプリ上でも。両方同時に走らせてたりするので、どっちも使うことになる。
大学の時によく遊んでいた友人から四半世紀ぶりにメールが届いた。いろいろと大変そうではあるが、何はともあれ連絡がついたのはよかっただろうと思う。詳細は省略するが、自分が今こうしてあるのはひとえに周囲の人々のおかげだなあということをあらためて思う。そういうことを常に忘れずに、ありがたく思い続けて生きていきたい。
リトルKを寝かしつけながら、寝てしまわないようあれこれ考えごと。
今週分の「NHKラジオビジス英語」を聴く。聴き取りに関してはほとんど問題ない。しかし、ポッドキャストはともかく、ホロライブENの人々の話などはまだまだ全然聞き取れないし。また、シャドーイングはなかなか舌が回らくてうまくいかない。まあ、話す機会なんて全然ないからいいといえばいいのだけど、単純に運動的な意味でうまく話せるようになりたいという気持ちがある。
昼間の続きに取り組む。またいろいろハマったり、見過ごしていたことなどがあったりして思うように進まなかったが、とりあえずやろうとしていたことはできた。次は、もうちょっと良い感じにするためのところを作る。
#日記 #1月30日
2023年1月30日
昨晩は、土井善晴さんの動画を少し観たりして盛り上がったので、『一汁一菜でよいと至るまで』をKindle版で買って、読みつつ就寝。
アイマスクをせずに寝たら、いつもより早めに目覚めた。その方がいいのかもなあ。寝足りない感じはあるけど。もっと早く就寝すればよいだけなのだが……。
ボードメンバーのミーティングで、社外の情報を持ち寄ってディスカッションネタにしようということをやっているのだが、最近全然話題提供できていないので、習慣づけてやらねばと、あらためて思ったりした。
帰宅すると、総務省の電波利用に関する電子申請・届出サービスのユーザ登録完了のお知らせが来ていたので、開局申請まで済ませた。これで手続きは終わったので、あとは待つのみである。
家で、ヤギサワWA23局、さいたまBX71曲と交信。後者は、室内でCQが聞こえてきたので、そのまま会話できた。
以前解けなかったD - Change Usernamesという問題が気になって、グラフ理論の基礎を学ぼうと「【グラフ理論とUnionFind木を理解する】AtCoder茶を目指す競プロ勉強会#4」を観たら、わかりやすくて「完全に理解した」状態になった。それで、問題もやってみた。すると、GitHub CopilotがUnionFindの実装を完全な形で書いてくれたので、ただ使うだけになった。すごいなあ。
iPadも立てられるスタンドを注文したのが届いた。出先で、iPadを立てておきたくなることがあるので、バックパックに常備しておこうと思ってのこと。普段は一枚板になるので、薄くていい感じ。
今日のブックマーク
- Takuya Kitagawa/北川拓也さんはTwitterを使っています: 「近年のAIの進化は実は理解されていない。 ChatGPTを筆頭に、信じられないレベルでAIが進化している。 そう、本当に信じられないレベルなのは、なぜAIがこんなにも「急激に」質が良くなったかを、誰も説明できないからだ。 おそらく発明した研究者本人たちですら。 どういうことか。 1/n」 / Twitter
- [森川嘉一郎さんはTwitterを使っています: 「新大学1年生の世代体験を確認するための年表、2022年度版。 マンガやアニメについて講ずる関係で、今年も作りました。](https://t.co/ePDkIV36Dn」 / Twitter https://twitter.com/kai_morikawa/status/1508991974510297088?s=12&t=uQ72k6XSAUncoRkYZ1vdmQ)
- [ところてんさんはTwitterを使っています: 「「地頭」という言葉を「今すぐできて、一生役立つ 地頭力のはじめ方」に出てきたフレームワークをベースにして、自分なりに改変して表現するとこんな感じかなー うーん、もうちょっといい図が書けそうな感じはしている](https://t.co/NnPd8doXob https://t.co/TUkeUSsrFE」 / Twitter https://twitter.com/tokoroten/status/1619896328443789313?s=12&t=7cr22es3j-AbQJxRb8y7EA)
- 【グラフ理論とUnionFind木を理解する】AtCoder茶を目指す競プロ勉強会#4 - YouTube
- Union-Find木を利用した無向グラフの閉路検出 - Qiita
#日記 #1月30日
2022年1月30日
朝、10時過ぎに起きる。昨日買ったSyuRoのブリキ茶筒を使い始める。
https://www.instagram.com/p/CZWfUI1vdC0/
Twitterを見ていたら、ナガオカケンメイさんが、民藝展を批判していた。曰く、いつから民藝はあんなにも高尚になってしまったのかと。それ自体はこれまでも繰り返されてきた批判であり、それ自体に共感する面もあるし、氏が現代の民藝的観点を持って実践していることに多大なる敬意を感じるものの、美術館でやる以上はしかたがないとも思う。一方で、清水穣氏の「民藝のための婉曲語法。東京国立近代美術館「民藝の100年」展レビュー」というレビューは、何が「民」であるかについて批判的な視線のない「教科書」的な展示だと評しており、より本質的である。
最近だと『アウト・オブ・民藝』という素晴らしい本で紹介された、柳が無視したものも含む民藝のオルタナティブな伏流というのもあるのだし、そういう意味でのキュレーションとしての意志を文字通り現在の「現在之日本民藝」として少しでも文脈づけるのがやるべきことだと思っうのだが、制度的にいろいろと難しいんだろうなあとも思う(協賛企業との兼ね合いや、来場者に関する目標、独自の視点を打ち立てるための研究体制・予算等の面で)。その中からでも、何かしらオルタナティブを打ち出すリスクを取ってほしかったとは思う。
Kとコーヒーを飲みに出かける。木澤佐登志『失われた未来を求めて』の続きを読む。その後、中目黒に場所を移して、さらにお茶しながら本の続き。
キャロルから始まり、チリにおけるサイバネティクスの実験と挫折、そこから始まるポスト・フォーディズムのオルタナティブなしの世界。大量の情報をあちこちに飛び移りながらドライブする文章に、めちゃ興奮を覚える。資本主義リアリティの強化に結果的に与してしまう再魔術化に対して、批判精神を持ってオルタナティブを提示する反脱魔術化を、というと図式的にすぎる整理になろうが、マーク・フィッシャーをそのように読み直すのが、彼の思想の「可能性の中心」ということなのだろう。
代官山蔦屋へ。本を何冊か買う。まだ買っておきたいものもあったが、キリがないのでやめ。いまこれを書いている時間がもう遅いので、記録はまた明日。場所を移して、細川重男『頼朝の武士団 鎌倉殿・御家人たちと本拠地「鎌倉」』を読み始める。大河ドラマの予習である(もう3話ぐらい過ぎてしまったけど)。細かい話はあまり知らないので、勉強になるなあと思いつつ、読み進める。帰宅して、さらに読む。その後、夕食を食べながら、「鎌倉殿の13人」の第4話を観る。
修論のアブストラクトを修正する。要項を見ていたら、本文が日本語の時は英語でアブストを書くようにということで、分量も間違っていた。1時間ほど使って、とりあえず、目安に近い感じで書き直した。明日、もう一度読み直して先生にメールしよう。水曜日が締め切りだ。その次は発表資料を作らなければならない。
RFAの8日目。さらに運動強度を上げて、28になった。敵の体力が全然減らなくなって、しんどいというよりだるくなってくる。もうきつくてやめようかなと思ったけど、World4のドラゴ戦までやって、クリア。ドラゴも全然体力減らないし、マジでウザい。この辺のゲームバランスはちょっと悪い感じがするなあ。強度が高くなったら回数が増えるのはいいけど、一度の戦闘にかかる時間が長いのはだいぶだれる感じがする。
2021年1月30日
午前は「遠隔教育システム工学」。会社の研修やらキャリアプランなどを考える上で、教育・学習の理論はつまみぐいしたりしていたのだが、あらためて総覧的に観ることができて、見通しがよくなる感じ。機会のデザインに加えてモチベーションのデザインも必要だという話で、ゲーミフィケーションがかなり最強感のある手法として紹介されていて、そうだよなあと思ったりする。また、昨今では「真正な」課題(作り物の課題ではなく現実の課題)に対して自ら手を動かして学ぶみたいなのがいわれているということで、そうだよなあと思いつつも、ピンとこない感じもしている。
午後はゼミ。進捗報告と、修論の計画書について話す。やりたいこととしてはいいんじゃないか?という感じではあったものの、単純にボリュームが多いから分割したほうがいいのでは?とか、評価についてやりたいことと評価とがマッチしていない、無理やり感があるとかいろいろフィードバックをいただく。どちらもその通りだよなあと思える内容。まあいったん全体像を描きだしてみないと、それなしに部分問題について述べても意味不明だろうから順番としてはこれでいいとは思うが、その中のどこにフォーカスするかは詰めるほうがよさそう。その上で、評価も考えていかないとなあ。でもまあ、そもそも実現可能性を確かめるために、技術的な検証もしてみないとなあなどと思う。
そんなこともあり、そういえばそういう話を書いた論文があったよなあと思いだして、「なぜソフトウェア論文を書くのは難しい(と感じる)のか」を読む。ソフトウェアというのが本質的に評価が難しいものであるとした上で、評価指標については、ソフトウェアの開発過程の困難さについてであるとか、自ら何かしら指標を立てて効果を主張するだとかあって、参考になる。なんかもうちょっと考えて、やろうとしていることにマッチした評価指標にできれば、そこから新規性にもつながっていくのかもしれないなあ。また次のゼミまでに考えてみよう。
Jetson Nanoのセットアップをしようとしたのだが、起動しなくなってしまって謎い……。疲れて眠くなってしまったので、20時過ぎ頃にベッドへ。そのまま寝入って夜中に起き出し、日記を書いたり。KがClubhouseにハマっていて、いろんなルームで話しを聴いている。また、Kの知人や従兄弟などもルームを開設して話したりしはじめたということで、ここ数日での爆発的な広がりようが想像された。
2020年1月30日
起きてすぐに仕事に取りかかり、ルーティンをこなしたり、ミーティングをしたり。昼は、依頼原稿の打ち合わせのために外出。在宅勤務を続けていると煮詰まってくるので、散歩がてらちょうどいい感じ。帰宅して、さらにミーティングしたり、セキュリティ系の施策についてアイディアを練ったり。
夕食にカレイの煮つけを作る。ちょっと似すぎて身が柔らかくなりすぎてしまった。もっとプリプリ感を残せるように調整するべきであった。その後、K君の推薦状に署名と押印をするために外出。飲みながら、研究計画やステートメントの話をする。
特に現代アートのアーティストは、ステートメントを述べることが多い。現代アートは、基本的にコンセプチュアルアートであるので、ひと目見てそれがなにを表しているのかは判然としない。であるからこそ、自らのコンセプトをステートメントとしてあらかじめ述べている。
自分自身も、自分のやっていること、やりたいことのコンセプトをステートメントという形で述べることによって、根源的に何に駆動されて活動しているのかということを明らかにするほうがいいのではないかと思っていたところ、落合陽一さんが「「物化する計算機自然と対峙し,質量と映像の間にある憧憬や情念を反芻する」(確かに34字で行動の全てを説明できる)」(有料記事)という記事を書いていたので、考えてみた。
その結果、「非 生命間の交通に現出する概念の生成変化=なめらかなシステムを実現する」という一文にまとめた。
2019年1月30日
鹿児島出張2日目。
鹿児島市との立地協定書の締結式。2年半前に、奄美市との協定を結んだとき以来の感じ。その後、鹿児島にオフィスを新設する関連でプレスリリースを出し、ようやくこのあたりのことを公にできた。
鹿児島の土地勘があまりにもないので、午後はそのへんを散歩したりしつつ、食べ歩き。「天文館むじゃき」で白熊、川久でとんかつ。特に後者は、「とんかつ」という概念そのものを揺さぶられるなにか、であった。
オフィスに戻り、今日の模様がKYTのニュースで放映されたのを見届け、山田孝之さんのお父さんのバーへ。ワインを一本空ける。さらに近くの「魚庄」で飲み食い。活き鯖があまりにもヤバい!たっぷりの、甘い油のノリ。こちらも「鯖」の概念が変えられた……。福岡もなんでも旨いけど、鹿児島はさらにそれ以上かも。
さらに、昨夜に引き続き「ワインバーしろ」へ。
2017年1月30日
新しい取り組みについて考えるのの続き。
終業後はジムでカウンセリング。筋肉量は徐々にあがってはいるが、体脂肪がなかなか減らない。インストラクターさんにも、「なんでですかねー」と呆れられてしまう。なんなんだろうなあ。前に比べたらお酒もあんま飲まないし、そんなにたくさん食べてるわけでもないと思うのだけど……。
というわけで、今日からちょっとメニューが変わった。結果が出ないとモチベーションも上がらないので、より飲食に気をつけて、ちゃんと減量に取り組むことと、水をたくさん飲むこと、これまで避けてたランニングマシーンもちゃんとやることに決めた。次のカウンセリングの時にはよくなっていたいなあ。
2016年1月30日
起床して準備した後、水道橋へ。@typeエンジニア転職フェアで行われるパネルディスカッションに参加するため。
かつ吉の水道橋店でランチ。時間があんまりなくてゆっくりできなかったのだが、渋谷店とは随分趣が異なり、大量の骨董をディスプレイしたすごい店内だった。その分なのか、渋谷店とは値段もだいぶ違っていたけど。
パネルディスカッションは、うち含めて3社のCTOがエンジニア組織について話す感じ。いつものような話をしたのだけど、聴衆がどう感じたのかはよくわからない。
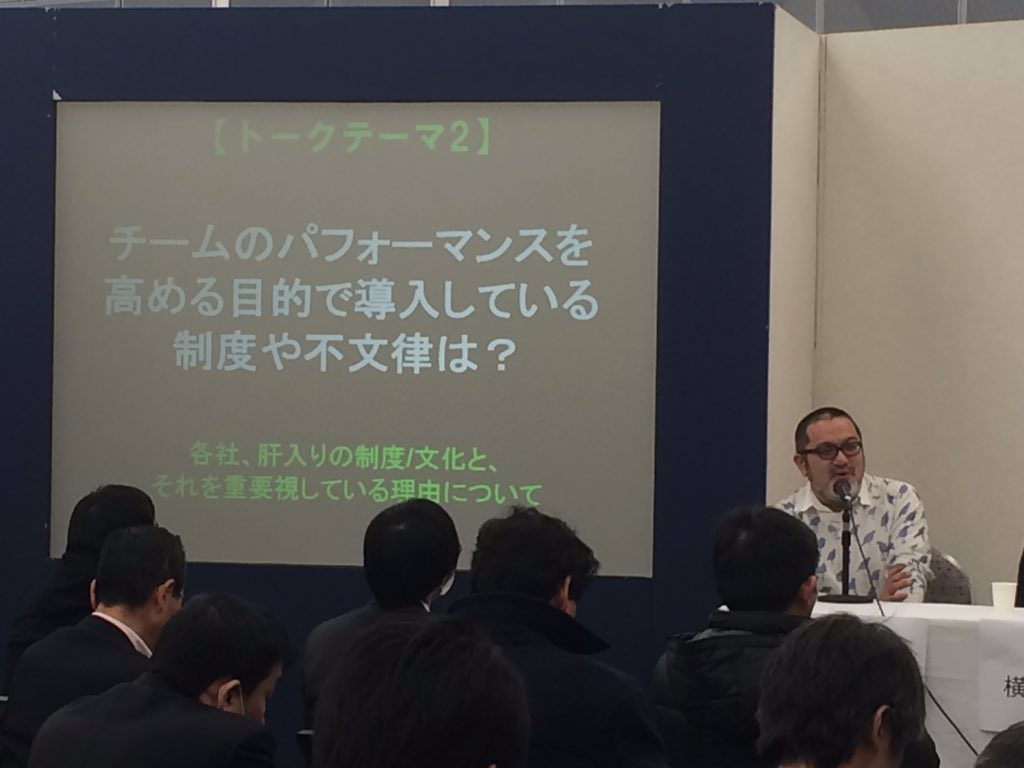
せっかくなので会場をぐるっとまわってみたのだけど、世の中にはたくさんの会社があるのだなあとあらためて思う。インターネット産業自体はなくならないだろうけど、いままでのようなWebサービス自体は随分変容するはずで、そうなった時にどうなるのかなあとか、あるいは、自分がもし他の業界に行くとしてやっていけるのかなあとか思ったり。
Web業界にきてから8年ぐらい、ただひたすら好きなことを好きなようにやってきたので、日本的な因襲に深く囚われた企業にもし行ったとして、生きていけるんだろうか、みたいな。実際、前々職はそういうのが耐えられなくて辞めたわけだし。まあ、そういうところには行かないからいいけど。
水道橋から神保町へ散歩。三省堂などを回ったりした後、ミロンガでお茶。
勝どきへ。かねますに行く。入店した時は、めちゃめちゃ混んでて不快に感じたし値段を見て「高い!」と思ったのだが、食べてみて感嘆……!久しぶりに食事によって衝撃を受けた。素材を惜しみなく使いつつ、仕事ぶりも丁寧。一口ごとに、ひたすら「旨いなあ……」とため息をついていた。
あとで知ったのだけど、エル・ブジのフェラン・アドリアが訪れて絶賛したり、「俺の」シリーズの創業者が「高級立ち飲み屋」という形態を参考にしたりしたそうな。
勝どきから銀座方面へ散歩。東銀座駅から日比谷線で帰る。出口屋で開運と玉川を買う。
帰宅して、ごろごろしたり、本を読んだり。





