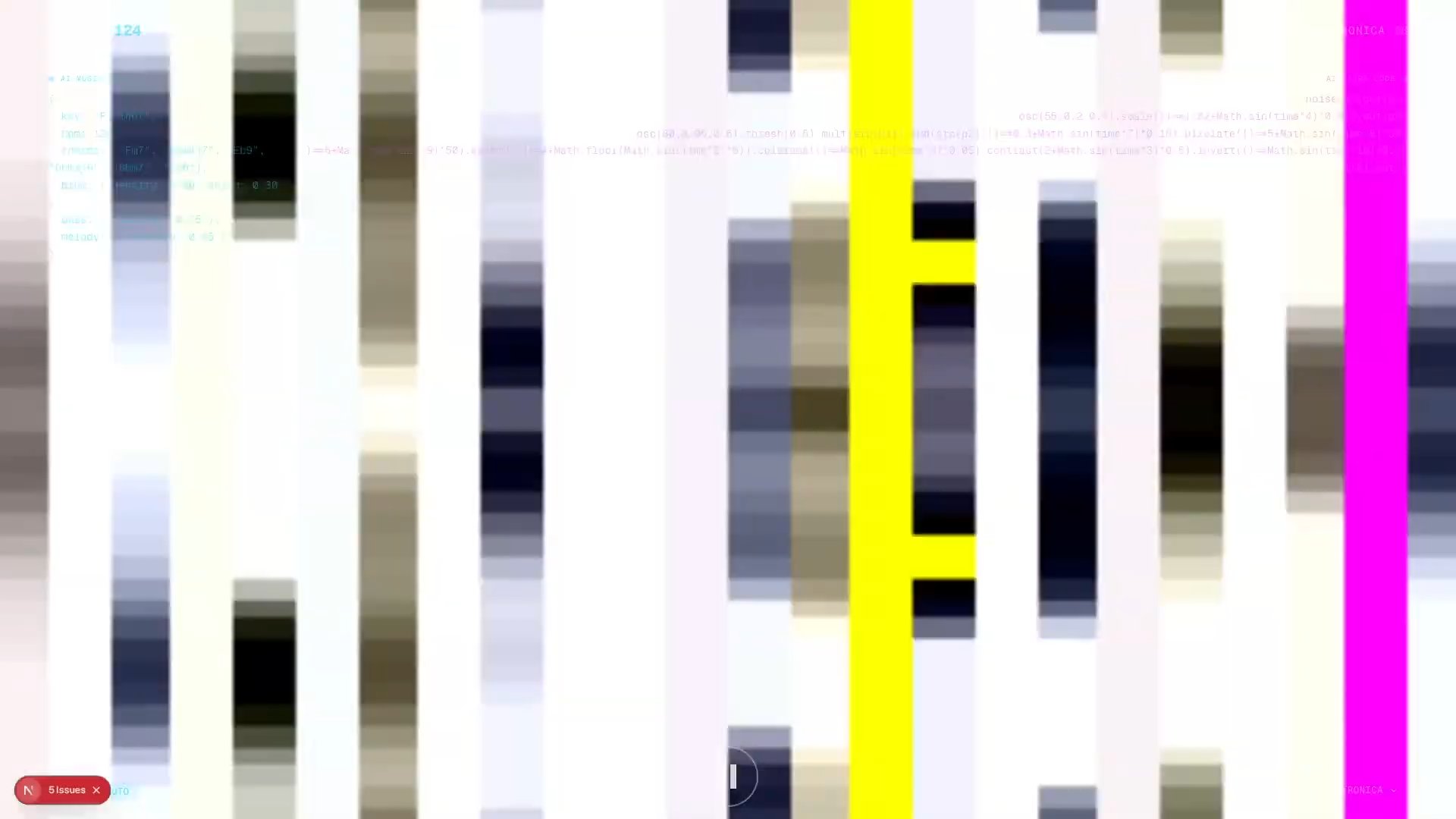12月1日の日記一覧
2025年12月1日
昨晩書いていたコードを用いて「♾️ Infinitape 📼」と題した無限ライブ放送をしこんで寝たところ、30分ぐらいで処理がスタックして映像も音楽もまともに出ない状態になってしまっていた。ひとまずはコンセプトができたので、ちゃんと動かないところを直したり、完成度を高めたりしていこう。
リトルKを保育園に送る。この頃のリトルKのビートボックスは、声も多用するようになって、バリエーションが増えてきた。しかし、いきなりえずき出しているように聞こえるので、知らない人が見ると驚くかもしれない。
夜は忘年会。あれこれとおしゃべり。
800円ぐらいだったのでKlackというアプリを買って使い始めてみた。キーストロークに合わせて、いい感じのキーボードみたいな音を出してくれるもの。没入感を高めることで、生産性向上に繋げるというアイディアアプリ。家ではHHKBを使っているのであまりよく聞こえないのだが、MacBookのキーボードを使っている時にはいいのかも。
エンジニアリングについての専門性がなければ、いくらAIで表面的にコードが書けてもしかたないんだ、というのは自分も思いはする。しかし、我々が生きている社会は人間が形成しているという意味では人為的なものだが、全然理解も制御もできてない。でもなんとかやれてはいる。そういうこともある。自然だってそういうものである。
2024年12月1日
昨晩からKとリトルKはK実家へいっている。明日帰ってくる予定。
ゼミのため、品川のキャンパスへ。発表スライドを見ていただき、予備審査会のプレゼンはなんとかなるんじゃないかという感じを持ってもらえたのか、わりとあっさりOKが出た。
今日は気分を休めようと、大手町の丸善へ行く。途中、東京駅で昼食をとろうと思ったのだが、どこも混んでいる。あれだけ飲食店が増えてもまだ足りない。以下購入。
- 福尾匠『ひとごと: クリティカル・エッセイズ』
- 学研の図鑑LIVE『地球 新版』
- 谷中瞳『ことばの意味を計算するしくみ 計算言語学と自然言語処理の基礎』
- 松岡正剛『空海の夢〈新版〉』
その他、Kindleで以下を購入。
- 乾敏郎・門脇加江子 『脳の本質 いかにしてヒトは知性を獲得するか』
- 人工知能学会編『人工知能と哲学と四つの問い』
- 岡典子『沈黙の勇者たち―ユダヤ人を救ったドイツ市民の戦い―』
- 宮台真司・近田春夫『聖と俗 対話による宮台真司クロニクル』
福尾本をひたすら読む。途中、少し寝たり、懸案となっている本棚の片付けをしたりしつつ、読み進める。非常に面白い。この人の問題意識みたいなことがようやくわかってきた。続けて、買ってきた図鑑を眺める。
本を読みながらクラシックの新譜を聴く。ユリウス・アザルの創意に感じるところがあった。
- Beethoven Blues ‑「アルバム」by ジョン・バティステ
- SCRIABIN – SCARLATTI ‑「アルバム」by Julius Asal, アレクサンドル・スクリャービン, ドメニコ・スカルラッティ
- Heard On Tour ‑「アルバム」by マックス・リヒター
- In A Landscape ‑「アルバム」by マックス・リヒター
移動中に聞いていた「コテンラジオ」でコミュニティナースという取り組みを主催している矢田明子さんの回を聞いて、大いに感銘を覚える。自分もなにごとか人の役に立てることがあるならやりたいとは思っているが、コミュニティに主体的に関わるみたいなやり方には疎外感をずっと覚えていた。この活動では、相互扶助を基本として、単に支援するだけでない形でできることをマッチングすることから始めるのだという。「偏屈じいさん」みたいな感じになりかねない自分としては、希望を持てる話である。
#日記 #12月1日
2022年12月1日
8時に起床。ベッドでごろごろしながらTwitterを眺めてしばらく過ごしてしまった。
今日も1on1やミーティングなどなどの日。隙間時間に[[生成AIモデルを試せるデモサイト]]を調べて、少しまとめてみたり。正面からこういう方面でやっていくことは難しいが、研究でいえば独自の問題関心からの領域については分もあるだろうし、サービス開発的にも適用領域をうまく作っていきたいと思っているところ。ともあれ、立ち位置をしっかり模索して行かねばならないと思う。
音楽を生成するようなものが、今の関心的に興味を引くところ。Mubertという音楽生成AIサービスのAPIを使って、text-to-musicをやっているコード(MubertAI/Mubert-Text-to-Music)を用いて、音楽を生成して遊んだりしてみた(提供されているJupyter Notebookは、ハック的な感じで面白いコード)。
[[https://scrapbox.io/files/6388afcf00760e001db85a1c.mp3]]
次のものは、CREEVO 自動作曲(作曲AI)で作ってみたもの。こちらは、曲を作るだけでなく、歌詞を元に歌にもしてくれる。すごい。
[[https://scrapbox.io/files/6388b41996c5c7001d534111.mp3]]
kindleのヘヴィユーザとしては、新製品が出るととりあえず買っておきたくなる。そんなわけでKindle Scribe キンドル スクライブ (32GB) 10.2インチディスプレイ Kindle史上初の手書き入力機能搭載 プレミアムペン付きを買ったのだが、でかいという以上にどう使えばいいのかわからない。手書き入力ならiPadがあるしなあ。どうしたものか。固定サイズのKindle本も十分読めるのは便利ではある(これもiPadでできるが)。
宮地尚子『傷を愛せるか 増補新版』を読み始める。
ワールドカップで1週間空きで、silentの8話を観る。春尾先生と奈々の話が切ないねえ。色々思うところはあるが、また後日。
今日のブックマーク
- [もよこ| UXコンサルさんはTwitterを使っています: 「UXリサーチャー デザイナーの皆さん 頷きすぎて首もげ注意ですw 学生さんや転職希望者の方にも このもどかしさや苦労は知ってほしい インハウスデザイナーさん達が6年間コツコツ積み上げてきた信頼・啓蒙、功績・実績に泣けてくる… (お話聞いてみたい) これをSMBCの名前出して出版した意義は大きい](https://t.co/UUUaeVi5ur」 / Twitter https://twitter.com/moyoko922/status/1597840209261236229)
- 竹内まりや楽曲のみで構成された1時間のミックス音源公開 - amass
- [r.sawadaさんはTwitterを使っています: 「NPOデフNet.かごしまが運営のグループホーム第一弾、Sign Terrace(サインテラス)、市より認可を受け明日からスタートとなりました! ろう・ろう重複者が「手話」で楽しく憩う家。 たくさんの方々にお力をいただきながらここまで辿り着けたことに感謝いたします!](https://t.co/Z6uOSsTNby」 / Twitter https://twitter.com/fluffytomoduffy/status/1597872645605031937)
- [やまかずさんはTwitterを使っています: 「AmazonがジェネレーティブAIを導入! 「Create With Alexa」は小さな子が「Alexa、物語を作って」と話しかければ、AIがアニメーションや効果音、音楽を含む5~10行のイラスト入りの物語を生成してくれるとのこと。アメリカで昨日からEcho Showデバイスで利用可能に。素敵](https://t.co/pqNB2aHYlf」 / Twitter https://twitter.com/Yamkaz/status/1597724626154819586)
- DJ Software for Mac - djay Pro by Algoriddim
#日記 #12月1日
2021年12月1日
今日は早くは起きられず。天気も良くないのでまあいいか。朝30分の研究タイムは、12月に入ったので予定していた通りに修論を始める。まずは、LaTeXテンプレートの準備から。ひととおり書ける状態になるまで持っていく。Bibtex周りで苦戦したが、とりあえずあとは書いていくだけというところまでいった。次は、IOTS2021の論文をはりつけていく作業。
昨日からの凝りと頭痛はまだ少し残っていて、ロキソニンを飲む。それでも治らないので、昼過ぎにまた追加で飲む。「ロキソニンSクイック」を初めて試してみているのだが、いつも使っている「ロキソニンSプレミアム」とは成分が少し違うみたい。やっぱそっちを買ってきて常備しておくことにしよう。いずれにしても、効き目が弱くなってきているのは確かである。結局、その後も微妙に治らず、ようやく寝る前ぐらいになってほぼ完治。一度痛くなると、2日間ダメになるなあ。そんなわけで、今日も夕方頃キツくなってきて、2時間ほど寝る。
夕食後、イギル・ボラ『きらめく拍手の音 手で話す人々とともに生きる』を読む。いわゆるコーダ(Children of Deaf Adults)の著者による本。「コーダ」という言葉を知って救われた気持ちになったとういこと、そこからこの本にもつながる活動が始まっていくあたり、聾文化におけるコーダの重要性についてあまりよくわかっていなかったが、切実なこととして認識した。同名のドキュメンタリも見てみたいなあ。ご両親が揺るぎなく強くある姿に、心打たれるところである。同じようなあり方は他の本でも何度も読んでいて、それが文化たる所以なのかもと思ったりもする。
もう一つ、現代思想編集部・編『ろう文化』も届いた。こちらは、現代思想誌の別冊で出ていたものの書籍化。これが出たときに「ろう文化というんだなあ」ぐらいのことを思った記憶はあったが、障害者運動的な文脈のもう一つの何かなのかぐらいに思ったままずっとこれまできていたのだが、様相はもっと全然違うのであった。今や古典的な文献となったこの本を、今あらためて読むのである。
2020年12月1日
今日から12月。仕事も学業も追い込み。多分、相当しんどい月になるだろうなあ。乗り切らねば。
今日は、チームメンバーとの1 on 1がいくつかあり、また、社長とのそれもあったので、いろいろおしゃべりすることが多かったなあ。新たなやっていきを見出したり、いま考えていることを話したりなどして、少しずつでも先に進んでいっているのではないか。
昨夜、先日書いたコードについて、そのままでは単に「こんなん作りました」というだけだが、「方式」と呼べるものにまで抽象化・一般化でして述べ切り、その一例としての実装だよということにできれば、論文になるんじゃないかと考えたりしていた。大学院では副テーマ研究が必修単位としてあって、そのためにレポートなり論文なりを書かなければならないので、この件をその成果にできたらいいよなあと思って、腰を据えて考え始めてみることにした。いろいろ知識が足りなくて詳細が詰められていないところもあるのだが、ストーリーはできそうな気もする。
というわけで、いま頭の中にある構造を論文の章立ての形で書き出し見て、それぞれの章に、こんなことを書くつもりというのをメモ書き程度に記載していった。そうやって書いてみるとやっぱり考えがちゃんと整理されてなくて、ちぐはぐな部分が出てくる。また、ここを押して考え、述べるべきだなというところも見えてくる。同僚からも助言をもらって、より研究としての水準が高まりそうな方向も見えてきたりもして、ありがたい。
ところで、JAISTでは学生にOverleafの有料プランを提供しているので、試しにつかってみようと思って使い始めてみた。エディタの方が編集は楽だが、思いのほかできがよくてびっくり。TeXの環境構築でつまるぐらいなら、これ使うほうがいいと思う。副テーマ研究の成果にするなら指導教員にレビューしてもらう必要があるので、その意味でもやりやすくていい感じ。PDFを送ってやり取りするとか、やりたくないもんなあ。
先日、「プロフェッショナル仕事の流儀」で、南麻布にある「茶禅華」のオーナーシェルの話を観た。それ自体も面白かったのだが、その中で出てきた客が料理を口にして「う〜〜〜ん、これは豊かだなあ〜〜〜www」みたいにいう姿が面白すぎて、Kとよく真似をしている。実際にその店にいって食事をしたら、確実にその場でも真似すると思う。
2019年12月1日
昼ごろの便で東京へ戻る.やや寝不足で,やはり機内ではずっと寝てた.気づいたら着いた感じ.出張中に,六本木にNorth Villageの新店舗ができたので,そのままそちらに寄る.思い立って落合陽一さんのnoteの購読を始め,過去ログを読んでいたらエモい感じになってきて,いろいろ整備.ジムを解約していたのだが,近所のANYTIME FITNESSに行くべく予約をしたり,表参道のアップルストアに寄ってiPhone 11 Proを買ったり.iPhoneは,機能的にはいまのでもいいやって感じなのだが,充電が全然持たないのがストレスなので.
帰宅して,iPhoneの移行.途中で止まったり,アプリの更新が全然進まなかったり,ちゃんと動けば楽なんだろうなーという仕組みなのだが,いろいろクオリティ低い.こういうところでストレスはだいぶあるよなあ.何度か再起動したりしてるうちに動き出した.そんなことをしつつ,Weekly Ochiaiのまだ観ていなかった回を観る.アウラや禅というテーマはともかく,ゲストの人選がヤバくて,かなりセンスがいい.どういう感じで選んでるのかなあ.
これまでサーベイしてきた内容をある種のフォーマットでまとめていく時期だろうということで,やり方を考えて,Google Spreadsheetでまとめはじめた.まず文献リストのマスタを作り,それを参照して文献をいろんな切り口で比較表としてまとめていく.そのへんは,やっぱスプレッドシートでやるほうが楽だろう.スプレッドシートからTeXにするWebサービスなどもあるので,論文にするときはそういうので変換する.さらに,VSCodeでTex文書を書けるよう環境整備を始めたのだが,いろいろ不満があっていろんな設定ファイルをいちからやりなおしたり,シェルをzshに戻したりとかあれこれやって時間がかかる.さらに,タイポしたりしてなかなかTex環境の検証が進まず,すっかり夜中になってしまった.
2018年12月1日
もう12月だ〜。
紀伊国屋書店で『抽象の力 (近代芸術の解析)』、『EYESCREAM(アイスクリーム) 2019年 01 月号』を買った後、インスティトゥト・セルバンテス東京へ、「クスコ写真学校:マルティン・チャンビと現代写真家達」を見に行く。マルティン・チャンビの写真は、厳格な古典的構図の中に、物語を感じさせる奥行きを持つものが多く、心惹かれる。また、その他にもよい写真もあり、もっと見てみたい気持ち。
さらにアンスティチュ・フランセへ移動し、「Coutume Kanak - presentation et signature du livre à l’institut français」に参加。ニューカレドニアのカナック族について、アーティストが調査した内容をまとめた本についての紹介プレゼン。フランス語なので、プレゼン資料の単語などを辞書で引きながら聞く。
夕食は、アンスティチュ・フランセから歩いて10分ほどの「すし北野」で。極めてまっとうな江戸前鮨という感じだなー。旨い。さらに、ル・パリジャンで一杯だけ飲む。旨い。
2017年12月1日
前にも書いた気もするが、NewsPicksでSHOWROOMの前田さんによるメモについてのインタビューを読んで、すごいなあと感嘆を覚えたので、メモをほとんどとらずにこれまで生きてきたのだけど、できるだけメモを取るようにしようと思って、意識するようにしている。とはいえ、突然できるようになるわけでもなく、すぐ忘れてしまうのだけど。
ノートにメモを取るというのはどうやってもなかなかうまくいかないので、とりあえずEvernoteを復活させ、Fasteverでテンポラリなメモを、ストック的なものはEvernoteのノートに取るようにした。読んだ本や、ネットの記事なども読んだはしからどんどん忘れていくし、固有名詞が全然でてこなくてもやもやすることも多くなってきたので、頭を鍛えないと……。
会社で、ファシリテーションについての勉強会。最近、ファシリテーションをする機会がないなーとあらためて気づく。また、立場上もどっちかというと引っ張る側なので、以前やってたこういうのも思い出してみるのもいいかもと思う。組織開発関連でいうと、マネージャーのメンタリング制度というのが始まり、今日はご指名いただいた方とランチ。いろいろ話を聞く。
夜はグループのDJ部主催のクラブイベント。準備がすごい。機材や音もよい。我々も1曲ライブにでたのだが、ビール飲み過ぎて歌詞がすっかり飛んでしまい、ヤバかった。
2016年12月1日
今月で今年も終りだー。
ジム。なんか寝ても疲れがとれない感じがするんだけど、ジムを頑張りすぎなんだろうか……。
帰宅したらLINE Pay カードが届いていたので、利用開始手続きをする。簡単だなあ。すごい。還元率2%ってのもいいし。というわけで、オートチャージ設定をして普段使いしてみることに。VISAカードしか持ってなくてApple WatchでSuica使えないと思ってたのだけど、Suicaアプリならそんなこともないみたい。LINE PayカードはJCBだけどApple Payには登録できないけどSuicaアプリには登録できるそうな。なんかよくわかんないけど、ともあれApple WatchでSuicaできるらしい。というわけで、Apple Watchがほしくなってきた。
決済の世界、どんどん動いててすごいな。ちょっとキャッチアップしないとなあ。
『入門 考える技術・書く技術【スライド編】』を読む。よい本。
2015年12月1日
今日から12月。朝、メディテーションを20分ほど。
昼食は牛すじ煮込み丼。たまにくるけど、美味しくて好き。
終業後、会社の飲み会でTUCANO'Sへ。席に着くなりダンスが始まって、ヤバかった。テンション高い。以前、元同僚とランチにきたことがある店だったのを思い出した。
帰宅して、antipop.fm (あんちぽえふえむ)のサイトをちょっと更新。
今朝は、メディテーションを始めるなり、哲学的・社会的にはどうかわからないし、エッジケースでは色んな課題もあるだろうが、だいたいの状況において自分が気分よく暮らせるためには、物事を(1)抽象的な実在(例: 法、制度、組織、論理的思考など)、(2)物理的実在(例: 目に見えるもの、現にそこにあると多くの人が考えるもの)、(3)それらをただ感覚する自分自身の3つだけに限定すればよいのではないかと思った。
まあ、極端な話ではあるし、幼稚な考えでもあるけど、実際たいていはそれぐらいに思っておくほうがいいことが多いのではないかなあと思う。その他のことは、社会的なことはともかく、自分自身の問題としては取るに足りないことだ。