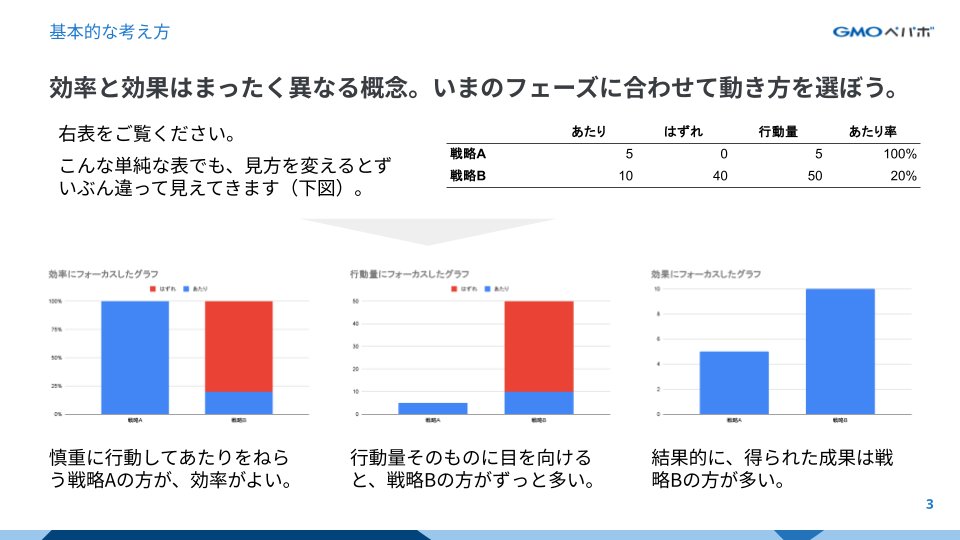3月17日の日記一覧
2025年3月17日
朝、リトルKを保育園へ送る。今日はいやがったりはしなかった。入口で靴もちゃんと自分で脱いだし。そのまま出社。先週金曜日のTechmemeポッドキャストを聴く。帰り道では、「まいにちフランス語」。
やたら忙しくて、夜まで落ち着くまもなくひたすらあれこれやっていた。週初めはチームで方針を数分話す会があり、当たり前といえば当たり前のことを確認するということをしている。
トミカの車をまだいくつか未開封でおいてあったのだが、リトルKがひょんなことからそれを見つけ、開けろ開けろと泣きわめく。無視して寝床に運んだら、今度は「おばけ!おばけ!」というので『おばけのてんぷら』を読み聞かせる。まだ序盤なのに「おばけは?おばけは?」といって、先を急かすのがおかしい。
『ベトナム語のしくみ《新版》』の続きを読む。この本はよいものだ。あれだけとっつきにくいと思っていたベトナム語が、だいぶすんなりわかるようになってきた。もちろん単語がまるでわからないので読めはしないのだが、構文解析はそこそこできるようになってきた。あとは発音をしっかりやるのと、単語だなあ。でもそこさえある程度積み上げていけば進んでいきそう。
先日ちょっとやってみてMCPまわりでハマってうまくいかなかった、MCPサーバとVRChatをOSC経由でやりとりさせてアバターを動かすというのをやってみた。まだまだうまく動かせないのだが、とりあえずAIからの指示でアバターが動くものはできた。
先日、「声」を出せるものは作ったので、あとあれこれそろえたら、面白いものができそうだなあ。そこまでやるかはわからないが。
2024年3月17日
大学院の講義を受講するため、品川へ。最後の時間は、期末テストが行われた。だいぶ苦戦したが、単位取れてるといいなあ。この際、もはやスコアは関係ない。とにかくこの単位が取れさえすれば、あとは博論を残すのみである。そちらもそろそろ始めないと。
「東京工業大学・上田紀行教授の最終講義をダイジェストでお届けしてみる。|東スポnote」という記事が流れてきたので、読んでみた。その中で、鈴木大拙『東洋的な見方』を引いたうえで、以下のように敷衍している。
松は松として生きる、竹は竹として生きる、あなたの中には松がある、その松を自由自在にマストであるということがあなたの自由なんだ。
世の中の自由の考え方は違います。松として生きている人に「あなたは竹にもなれへんな、梅にもなれへんな、山にもなれないし、河にもなれないなぁ」で、こういうことができないじゃないかと指摘して、「お前は不自由な奴だなぁ、松にしかなれなくて」というのが今の自由という考え方かもしれません。
東京工業大学・上田紀行教授の最終講義をダイジェストでお届けしてみる。|東スポnote
こういう話はよくいわれるが(「置かれた場所で咲け」みたいな)、まったく違うと思う。
鈴木大拙のような人はともかく、それ以外のほとんど(もちろん自分も)は、「松」でも「竹」でもなく、ただアモルフな動物的生を生きるだけである。だから、「松」であることの必然性を自在に生きる、みたいな話は違っていて、なんだかわからないものとして、自然に生きるだけである。
しょっちゅうDISっているが、現代の先鋭的な思考家すらも「AIが発展しても人間に残されたものがある」みたいな、極めて凡庸な発想に陥ってしまうのだが、それは「松」ではないかもしれないけど「竹」ではあるかも?みたいな話に過ぎない。実際は、どちらでもないのである。
一方で、しかし人間にはAIには実現できないなにがしかがあるように見えるという実感があるのもまた自然なことではある。まだ解明されていない、そして将来にわたってされることもなかろうことが、人間にではなく社会にはあり、それを人間の本質であると短絡しているからである。
いまこそ、社会をみなければならない。情報科学にたとえていえば、システムを考えるべきなのに単体の端末のみについて考えるから、AIにはない人間の本質なんて話になる。端末にそんなものはない。本質はシステムを構成するネットワークに宿っているのだから。
そういう意味でも、情報科学の最先端は、AI関連についてはいうまでもなく、そこからさらに進んで極めて面白い展望を開いている。たとえば谷口忠大氏が10年以上前から提唱している「記号創発ロボティクス」が開く、言語の社会的創発に関する構成論的探求がそれである。
https://twitter.com/tanichu/status/1768431204196569470
僕はなにもこの話からそういう考え方を始めたのではなく、リチャード・ローティやデリダ=東など、人文学によって開かれた視座に影響を受けて考えてきた。そんなわけで、あらためて社会に対するこうした視座をもってこれからの思考を進めていきたいと思っている。
2023年3月17日
どうにも寝た感じがあまりしないのだが、頭痛は治ったような気がする。首まわりの違和感はほぼなくなった。この1週間、頭痛を抱えながら激しくマルチタスキングしてたし、ずっとテンションが高かったので、さすがにぐったりと疲れた。
出社して予定をこなした後、赤坂中央クリニックへ。尿酸値は4.5まで下がった(相変わらず単位を憶えられない)。問題のない水準である。このまま維持していきたい。ただ、中性脂肪、コレステロール、クレアチニンなどの他の数値は特に良くなっていない。特に前二者はとにかく減量するしかないもの。少しずつ減量基調だったのだが、このところ少し戻ってきてしまっているので、あらためて留意しなければ。
さらに日本CTO協会関連の仕事をして、今日は終わり。かと思ったら、いろいろと細かいタスクがあれこれ飛び込んできて、バシバシ片付けていく。
段ボール箱が届いたので、スキャンに出す本を詰めていく。文字ばかりの本は基本的にスキャンしてしまおうという方針を決めたので、あまり考えることもなく詰める。考え始めると進まない。物理本でなければならないようなもの、大版の資料的なもの、アート関連は残しておく。
論文を書かないとなあと思いつつ、ぐだぐだしてしまう。ChatGPTで遊んだり、AI関連の情報収集をしたり、YouTube動画を眺めたり。
論文を書くに際して、最初から高い完成度のものを書こうと気負ってしまっているせいで描き始めが遅くなってしまっているので、ブログを書くぐらいの気持ちでまず初稿を書き上げてしまおうと思ったら、わりとするすると書けるようになった。2時間弱でイントロを書き上げることができた。リファレンスもあまりなく、かなり雑な感じではあるものの、言いたいことのコアは一応ある。とにかく書いて書いて、書き上げることが重要だ。週末で一通り描きあげたい。いけるかな?
今日のブックマーク
- やはり予想を超えてこなかったGPT-4と、GPUの未来、ホビイストへの手紙 – WirelessWire News
- ついに来る!TypeScript5.0の新機能 - Speaker Deck
- ChatGPTでブレストをすると、無限にできてヤバイという話|けんすう
- Kubernetes の運用効率化を ChatGPT で実現する 障害対応編 | sreake.com | 株式会社スリーシェイク
#日記 #3月17日
2022年3月17日
朝30分の研究タイムから。ジャーナルの事前アドバイスで「「設計と実装の複雑さを低減する」といってるのだから、それらについて定量評価する必要がある」というもっともな助言をいただいており、どうするか少し考えてみたりしていた。比較した手法が、ソースコードを公開していない中でどうしたらよいのだろうと、詰まっていたのであった。ちょっと研究から離れて、この仕組みを実際に使うべくメリットを売り込むとしたらどうするか、という観点で考えてみるといいかもという着想を得た。
その後、夜までミーティングや1 on 1など。その後、隔月で開催されている「K-Ruby#29 LT&もくもく会」に参加。今回もLTをした。しかし、LTの持ち時間の最大値として示されていた10分ぐらいで話したかなと思っていたら、結果的には15分ぐらいだったようで、反省。内容は、ここのところElixir関連でやったことをZennにまとめていた記事の紹介。今回はスライドがないので、動画を撮ってYouTubeにアップしておいた(サムネ的なものを雑に作ってみた。いかにも素人動画という感じである)。
https://www.youtube.com/watch?v=4_6kS2WYVHQ
夕食をとりながら、NHKプラスで「日本人のおなまえ」の最終回を観る。というか、Kがわーわーいいだしたので何事かと思ったら、最終回であるという旨の案内を見て驚いていたのであった。食事時にiPadでNHKプラス経由でNHKの番組を観るということをこの数年続けているのだが、その中でも継続的に観てきた番組だし、面白い内容が多かったので残念である。今回は総集編。また別の切り口で、こういう番組をやってほしいなあ。
花粉症で思考にもやがかかった感じなのと、体のだるさみたいなのも少しある状況が続いていて、決定的にしんどいわけでは全くないが、微妙な状態が続くのが嫌という感じ。
机に向かうのも面倒で、ベッドに入って千葉雅也『現代思想入門』の続きを読む。現代思想における「脱構築」三題噺としてのデリダ、ドゥルーズ、フーコー、その源流としての形相と質料の相剋の変奏としてのニーチェ、フロイト、マルクスについて紹介したのち、ラカン、ルジャンドルと続くあたりまで。極めてわかりやすい。しかし、実はそのリーダブルな外観にそぐわない過激なことを言っているはずで、そこが著者のバランス感覚として興味深いところである。
2021年3月17日
昨夜、寝る前に首周りに違和感を感じていてヤバいな―と思っていたら、朝起きたら首凝り。しばらく仕事していたのだがやっぱりだんだん痛くなってきて、頭痛薬を飲んで寝た。このパターンは初めてな感じ。最近ちょっと根詰めてやってたから凝ったのかなあ。ついつい熱中してやっているとストレッチを忘れたまま寝ちゃうから、気をつけないと。そういう状況でも、ちゃんとやる癖をつけないとなあ。
スパイラルで開催中の武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科クラフトデザインコース 卒業・修了制作展 2020を観る。その中で、上村結さんという方の作品に衝撃を受けた。写真を転写したテキスタイルの中に綿を詰めてクッション上にしたものに、立体感を与えるピンポイントの刺繍(たとえば、ラインになっているところに縫い目をつけるとか、ゴミ袋のしばっているところに何本か縫いを入れるとか)。写真を用いた表現として、めちゃくちゃ新しいしかっこいい。インスタグラムもやっていて、作品もいくつか観ることができる(が、写真だとわかりにくい)。
最近できたというiittalaの旗艦店へ寄る。カフェでご飯を食べたのち、Kが注文してあったアルヴァ・アアルトがデザインした花瓶の特別版みたいなのを引き取る。iittalaが作るような北欧デザインみたいなのはあまり好きでないものが多かったりするのだが、まあ偏見みたいなのがないわけではなく、カイ・フランクのものなどは好みだし、iittalaで作ったのではないものの中にはかなり欲しい物もあったりして、あらためてその辺もみていってもいいよなあという気もする。そういえば、スパイラルの5Fのcallに置かれていて知った藤本健さんの木工のうつわがめちゃくちゃ好みで、むしろそっちを集めたいところ(けっこう値が張るのだが……)。
帰宅して、いろいろやりたいところではあったが、なんかだいぶ疲れており、早々に寝る。
2020年3月17日
朝からあれこれやって、夜はCTO協会の定例ミーティング。MOMENTへ行く。グローバルOKRとしてのSDGsに対して、カンパニー、チーム、個人としてどう落としていくかという構造について考える。
2019年3月17日
今日は株主総会と、近況報告会。大過なく終わり、運営チームに感謝。その後、運営の慰労会。近くのワインバーローディで1次会、からの、恒例の磯丸水産へ。
帰宅して、「美術手帖 2019年4月号」を眺める。「アウト・オブ・民藝」という企画に関する対談記事が面白い。本も出るとのことで、期待。
本を読みながら、例によってワインを飲んでいたのだが、メンドーサのマルベックで、コルクがひどくてげんなりしたのだが、すごいスケール感があり、感嘆。
2018年3月17日
「ある光」以降の小沢健二さんのシングルをプレイリストにまとめたものをかけながら洗濯。ここ数週間の習慣。
「写真都市展 −ウィリアム・クラインと22世紀を生きる写真家たち−」を観に、自転車で21_21 DISIGN SIGHTへ。階段を降りていくと、なにやらトークイベントが行われている。作品を出展しているTAKCOMさんとドミニク・チェンさん。きっと面白いだろうので聴いてみたかったのだが、満席な上に、ちょうど終わるところで残念。ウィリアム・クラインの写真そのものは入り口に少し展示されてあるだけ。こんな風に「都市」という題材をプレゼンテーションできた時代に対する懐かしさのような感じを覚える。
TAKCOMさんのウィリアム・クラインの写真を使った映像は、最初のうちは全然乗れなくて、むしろややいらいらしてしまったのだけれども、鏡をみながら顔の様子を確かめる女性がコラージュに覆われていくあたりから気分も乗ってきて、壁面全体に多数かけられたディスプレイを使っての都市シリーズの映像に至ると、かなり興奮して観ていた。ウィリアム・クラインのかっこよさを、さらに引き出す素晴らしい映像だったなあ。
映像コーナーを出て、写真の展示を見て回る。いくつか、気になる作品があった。まずは、多和田有希さんの“I am in You”がよい。海の写真の、波打ち際で泡立ったあたりにたくさんの穴が空いている。水の青さが残っているところを何らかの方法で焼いて空けたようだ。そのことで、なぜか泡立ちが写真の表面を超えて、生々しい物質的な感触をもたらす。写真をぶらさげて展示しているのも含め、面白い表現。ショップで、これまでの作品を紹介した小冊子が売られていたので、購入。
その他、先日のアートフェアでも少し観た沈昭良さんや、勝又公仁彦さんの作品に惹かれるものがあった。特に勝又公仁彦さんについて、画面の雰囲気が全然違うにもかかわらず、なぜかわたせせいぞうを思い出したりしたのだが、それはともかくとして、ショップで売られていた小さな作品集を見ると、ロバート・モスコウィッツ風(というかそのまま)だったり、ゲルハルト・リヒター風な抽象的な作品などもあり、ちょっとおもしろい。
ミッドタウンのTIME & STYLEで、中里伸也さんの作品を眺める。以前にもたまたま寄ったことがあって、その時も強い印象を覚えたのだったが、今回は意を決して買うつもりで。とはいえ、あまり大きな作品は部屋におけないので、展示されていた中では一番小さなサイズのものを選ぶ。「これがほしい」と思ったものについてきいてみると、先約済であるとのこと。しかし、展示してない作品が3点ほどあるということで見せてもらえたので、その中からひとつ選んだ。特注の額の制作の関係で、納品がGW明けになってしまうとのこと。しかたあるまい。中里伸也さんの作品、他にも買いたいなあ。
青山ブックセンターで『アート・パワー Art Power Boris Groys』、『たまもの (ちくま文庫)』などを買う。帰宅して、本を読んだり、モランディ風写真の習作を一枚作ったり。先日のよりはややよくなったが、まだ自分の頭の中にある絵には遠い。
別に写真を撮りたいわけではなくて、自分のイメージしている絵を作りたいだけなのだが、そのためにもまずは写真の技術についてもちゃんと知っておく必要があるだろうと思ったので、あらためて基本的な概念やカメラの操作方法などを、言葉を調べたり、マニュアルを読んだりして学習しているところ。しかし、あれこれ試してみないとなかなか身につかないなあと思ったので、いろんなシチュエーションで練習しないとなあ。
2017年3月17日
ささっと帰宅。明日にそなえて寝る。