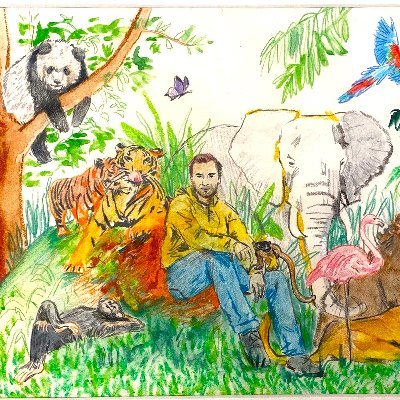4月2日の日記一覧
2025年4月2日
夜中までVibe Codingしていると過集中になって、気づくと芯まで体が凍えている。タオルケット、毛布2枚、羽毛布団をかぶっているので、普段はしばらくしたら暖まってくるのだが、そうなると朝になっても寒い感じがある。今日は喉が少しヒリヒリする感じになった。早めに対応して、ひどくならないようにしなければ。
今日は保育園の前に病院に連れていくということで、Kが見送り。リトルKは、いつもは「ママ、ママがいい」とばかりいってるのに、僕が行かないとなると「パパはー?パパはー?」という。
今日は会社で入社式(グループ全体の入社式が昨日はあったので)。朝に式をして、夜は懇親会。年末旅行以来である。若くて優秀な方々ばかりで、楽しみ。それらイベントの間、ミーティングとミーティングの合間に新規事業向けのコーディング作業をふたつしあげた。
Vibe Codingなどといわれはじめたのは今年の2月である。
しかし、自分も遅くとも1年前にはそんな感じで新規事業のためのプロトタイプをたくさん作っていた。当時はまだコーディングエージェントが発展していなくて、Cursor Composerもまだ出ていなかった(出たのは2024年の7月Changelog - Jul 13, 2024)。当時はCusorのChatで複数ファイルを編集してくれてapplyをぽちぽち押していく感じで、ドライバーは人間であった。
一方、Clineのファーストリリースは2024年7月(Release v1.0.4 · cline/cline)。Cursor ComposerがAgent化したのが2024年11月(Changelog - Nov 24, 2024)。このあたりから、本格的なAIコーディングエージェントの時代が始まった。画期となるのは、ドライバーがAIエージェントになり、人間はナビゲーターになったことである。
一方で、Vibe Coding的なノリに近いことは2007年に登大遊氏が書いていた。当時は、氏のような天才にしか不可能だったことが、今では少なくとも物量に関してだけでいえば、誰にでもできるようになった。エンジニアリング的な観点であれこれ物言いはもちろんあるにせよ、天才にしか成し得なかったことが一部「民主化」されているとはいえる。
Xにもポストしておいた。
酔い覚ましもあり、会社から歩いて帰る。今日もNHK講座のノルマは達成できず。といっても、スペイン語、イタリア語、英語、ロシア語、中国語、韓国語の講座を聴いてはいるのだが。このやり方は自分に合ってる感じがある。
2024年4月2日
日曜にはまだつぼみだった桜が今日は満開になっていて驚く。こんなにもパッと咲くものだっただろうか。いつもそんな感じだったのかもしれないし、そうでないかもしれない。いつの季節も、毎年こんなだったっけ?と、同じようなことを思ってる気がする。
昨夜は『Jazz Theory Workshop』を読んでいた。このところ音楽理論について本を読んだり動画を見たりしているため、きいたこともないということは少なくなってきた。演奏に使えるかどうかは全然別の話ではあるけど。作曲には活用できそう。
音楽理論についてはこれまでにも少し本を読んだりはしていたのだけど、あまり深くはやれなかった。DTMを始めたことが、これまでとは違う。作るとなると理論的な知識がまったくいらないということはなかろうので、興味が続いているのだろう。
そもそも音楽理論に興味があるのは、単純にエンジニアリング的な興味関心があるからということでもある。なにかしらの体系=システムがあるとき、それがどのような機序で動いているのかを知りたいということである。そういうのは昔からあるだろう。
でも、理解したいぐらいの動機だと途中で別のことに気が散ってしまう。やっぱり制作するために知ることの方が、動機として強いようである。まあ、それが普通だろうとも思うけど。そういうことからも、制作のための学習を組織するのが良かろうと思う。
とはいえ、何かを理解したり知ったりしたいという欲求もあるのであり、しかしそちらはもろい。そういうのも、直接的に制作へと向かわせられればいいんだろうけどなあ。学びをまとめるとかには面白みを感じない。どうしたものだろうか。
2023年4月2日
ここのところ就寝前に『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』を読んでいるところ。今のところは集積回路の初期の頃の復讐という感じ。それでも十分面白いのだが、これからに期待。3時過ぎに、リトルKに授乳してから寝る。
明け方に起こされて、Kに引き渡してまた寝た。9時過ぎに起きたが、全然眠気が取れなくて、だるい感じ。Kがもう出かけるというので、起きる。というわけで、今日はしばらくリトルKとふたりで留守番。寝つかせて、その間に論文の続きをやろうと思っていたのだが、全然寝ないし、ずっとぐずっている。しかたがないのでボバラップで包んで落ち着かせ、作業。
もう人生の半分ぐらい生きたことになるのかと思ったりすることがあるが、しかし昨今の情勢を見ていると、もう半分はこれまでとは比較にならない密度になりそうだから、あと半分でももっとだいぶ楽しめそうな気もする。
AIが爆発的に発達してるからこそ、芸術・芸能によって教養を身につけることはますます重要なんじゃないかと思う。情報はAIがいくらでも要約できるが、教養的体験とは人生そのものであり、情報のように要約することはできない。情報的な「貧しさ」に翻弄されないしなやかな教養を。そんなことを思ったりして、これでは浅田彰さんや東浩紀さんがある種の保守的な言説へ展開したのと同じだよなあと思う。ダサいけど、しかたない気もする。
生得か環境か、というフレームがある。人間の能力のうち、進化の過程において獲得したpre-trainedな部分を生得的なこととして重視するか、生まれた後にfine tuningしたりreinforcement learningしたりして獲得する環境的なことを重視するか、わりと多くのことがそんな話なんじゃないかと思える。答えは、場合によるし、どっちもだいじ。
論文作業にも疲れてきたので、リトルKをお腹に乗っけて、眞木啓子『ようびの器 ものみな美しき日々のために』を読む。そうしているうちに、Kが帰ってきた。
散歩に出かける。お茶しながら本の続きを読んで、読了。「眼福」という言葉がふさわしい。すっかり心が洗われた気がする。こういうのを忘れずに生きていきたい。その後、帰宅して夕食を作る。本を読んだこともあり、ちょっとちゃんとやるかなという気持ちになる。Kが高島屋でお弁当を買ってくれたので、汁物だけ作る。昨日、冬瓜を買っておいたので、スープを作った。旨い。
リトルKの世話などをした後、論文作業の続き。だんだん疲れて雑になっていく感じ。しかし、とりあえず最後まで終わらせた。ページが半分ほど余ってしまったので、実装の詳細について書き足す。それでも2/5余っている。微妙な余白。投稿する予定のカンファレンスの過去の予稿をいくつか見たら、それぐらい余らせてるものもあったので、まあいいかという気もする。
日付が変わる頃に、坂本龍一さんの訃報。
今日のブックマーク
- SNSの負の側面に、わたしたちはどう向き合うべきなのか? 東大教授・鳥海不二夫が考える「情報的健康」のこれから | WIRED.jp
- Anond AI開発日記 - Hatena Developer Blog
#日記 #4月2日
2022年4月2日
10時ごろに起きて、チェックアウトの準備。ちょっと行ってみたいところがあって出町柳まで出向いたのだが、開いてない。しかたがないので祇園へ行き、お茶しながら橋本治『大江戸歌舞伎はこんなもの』の続きを読む。その後、八坂神社から円山公園へ一周歩く。席が空いていればビールの一杯でもと思ったのだが、生憎満席。スタバでコーヒーを飲みながら、『作者の家〈第1部〉―黙阿弥以後の人びと』の続きを読み、読了。
その後、16時40分の回の都をどり「泰平祈令和花模様(たいへいのいのりれいわはなもよう)」全八景。3年ぶりの開催。
- 第1景 置歌(銀襖)長唄
- 第2景 上賀茂社梅初春(上賀茂神社)長唄
- 第3景 夏座敷蛍夕(洛中町家)別踊 長唄
- 第4景 京遊戯色々(都大路)別踊 長唄
- 第5景 那須与一扇的(八島)別踊 浄瑠璃
- 第6景 勝尾寺紅葉揃(勝尾寺)長唄
- 第7景 宇治浮舟夢一夜(宇治八宮邸)別踊 長唄
- 第8景 御室仁和寺盛桜(仁和寺)長唄
前回は2010年4月10日に観たので、それ以来12年ぶりである。耐震工事中で、歌舞練場ではなく南座。しかも3年ぶりの開催。イベントごととしては、やはり以前に比べると寂しい感じもあるが、舞台は変わらず華やかで、感激する。それにしても「京遊戯色々」の竹馬と鞠で遊ぶ姉弟がかわいかったなあ。
その後、京都駅でKの旧友家族と鰻をいただく。新幹線内では、1時間ほど眠ったのち、『大江戸歌舞伎はこんなもの』の続きを読み、読了。帰宅して、村祐亀口取り茜ラベル無濾過生原酒。上等の和三盆のような甘みを持つ村祐には親しんできたが、こちらは打って変わって柑橘的な酸味が強い、これもまた個性的な味わい。驚く。届いていた『作者の家〈第2部〉―黙阿弥以後の人びと』を読み始める。
明日は朝から必修の授業を受ける必要がある。
2020年4月2日
リチャード・ローティに思いを馳せる。僕が一番受けた彼の文章「トロツキーと野生の蘭」のことを思い出す。そういや日本語では読んだことなかったなと思って、その文章が収録されている『リベラル・ユートピアという希望』を注文した。
2019年4月2日
仕事したり、引越し準備したり。夜は、ワイン飲みつつ、不用品を捨てたり、掃除したり。僕は相対的にものを買うことが少ないと思うのだけど(本以外は)、それでも捨てるものが大量に出てきてうんざりする。できるだけものを買わないようにしようとあらためて思うのだけど、そうもいかないのだろうなあという気もする。
ともあれ、今日は7年住んだこの部屋の最後の日。だが、感傷にひたる間もなく、ひたすら片付けをしているのであった。しかしまあ、思い返すと7年ってそれなりに長いよなあ。35歳だったのが、いまや42歳。当時とは立場も視座もずいぶん違う。あるべきほどに成長できたかはわからないが、この会社に入らなかったらいまあるようにはなれなかっただろうと思う。
2018年4月2日
新卒入社の方々がやってきた。夜は、入社式と歓迎会。
同僚とTOSHABUTSUというアートユニットを作るという話になり、さっそくサイトを作り、作品を発表した。こちらはTHE GALLERYとは別に、アーティストコレクティブとしての活動であり、また、カジュアルにアウトプットをしていく場。
TOSHABUTSUという音だけ聞くと、一瞬「盧遮那仏とかの仲間かな?」と思えて尊いニュアンスがあるし(「断捨離」メソッド)、アウトプットをもっと「吐瀉」ぐらいの感じで気軽に捉えてもいい、そんな意味のこめられた名前。また、漢字で「吐写物」と書くことにし、新たなコンセプトとすることは、アラーキー的な造語感覚の引用でもある。
ってのと、あとはspewがめちゃかっこいいので、そこからパクったというのもあるな……。

2017年4月2日
S氏らと高尾山へ。高尾山には何度かきているが、リフトを使わずに登るのは初めてな気がする。けっこう坂が急でしんどかった。帰りはもうちょっと森っぽいコース。草木に対する知識があればもっと楽しめるだろうなあと思って、集中的に学習しようというk持ちをあらたにする。図鑑でもまるごと記憶するか。
下山して、最近できたらしい温泉。きれいで、現代的な温泉。湯もよかった。あがった後、ビールを飲みながら『「全世界史」講義 II近世・近現代編:教養に効く! 人類5000年史』を読む。
京王線で新宿まで出て、「テン・テン・テン」という日本酒のカップ酒をとりそろえた店で夕食。料理もよかったし、またこようと思う。
中目黒でおりて、目黒川沿いを少し歩く。桜が満開。