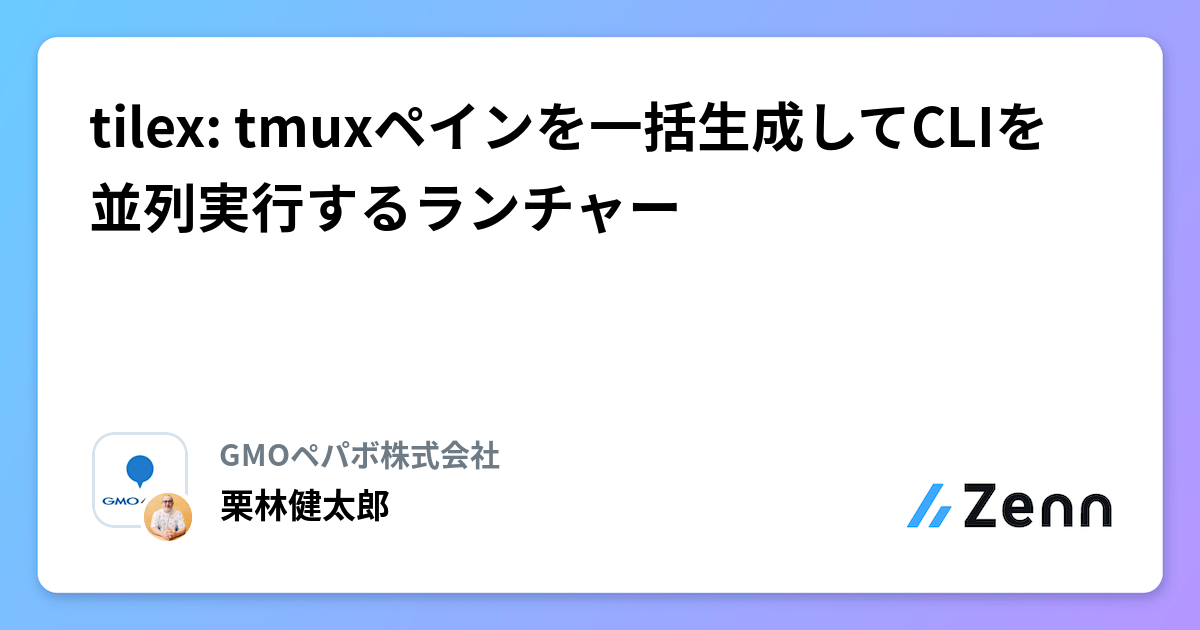6月3日の日記一覧
2025年6月3日
昨晩も遅くまでコーディング。中毒。
朝起きて、昨日捕獲したクワガタをさっそくリトルKに見せる。全然怖がる様子もなく、大はしゃぎしていた。はさまれてちょっとちくっとしたのにはびっくりしたみたい。その後、保育園に行く途中で公園に寄って、「ばいばい」といって返した。今度はカブトムシなども見つけられるといいなあ。いるにはいるはず。
『エンジニアリング統括責任者の手引き』をいただく。ざっと読んでみたが、すごい本である。この本があったらもっとうまくできたろうなあとも思うし、いまの活動をこれにそってあらためて見直してみようというきっかけになった。一方で、こんなにたくさんできないとならないの?と圧倒されちゃう人もいそう。しかし、いまそういう役割の人もひとつずつ実地にやっていって身につけてきただろうので、そういうつもりで読むと良さそう。困ったときに相談する先みたいな。
ミーティングの合間に技術調査・検証の続き。ちょっと色々厳しそうなので、方向転換のためのアイディアをいくつか考えたりした。
リトルKが39.5度の熱ということで、急遽帰宅する。一度もどしたということだったが、そこからさらに2回もどした。解熱剤の坐薬を投入。しばらくしたら、少しはマシになってきた様子。気分を落ち着かせるために、一緒に昆虫図鑑を眺める。蝶と蛾の区別をしようとして、「ちょうちょ?が?」「が、ちょっとこわい」などといっていた。
Claude Codeをコマンド一発で並列実行したいと思って、簡単なシェル関数を書いて「tilex: tmuxペインを一括生成してCLIを並列実行するランチャー」という記事にした。普通に便利かも。今も日記を書いている裏で、作った関数を使って、あるリポジトリに対してClaude Codeを4つ並列実行してコードを書かせている。
今日こそ早く寝なければ。
2024年6月3日
昨晩は動画サイトを「ストレートネック なおしかた」みたいな感じで検索してでてきた内容を実践してみた。ひとによっていうことが違っており、信用ならない。とりあえず自分に当てはまりそうなことを試してみる。ストレッチのルーティンを、まずは作る必要があろう。
昨日から予兆があってそんなことをしていたのだが、今朝はしっかり凝りが発生し、弱い頭痛が続く。さっそく習い覚えた運動をしていくが、微妙におさまらない。効いている感じはするのだけど。強い頭痛に発展しないか、気が気でない。雨もふり始めたし。
展覧会「遠距離現在」か最終日なので、午前にいってきた。企画意図を読むと「テクノロジーによる新たな疎外」のようなつまらなさを感じるのだし、実際にそういう展示も多かったのだが、いくつかは、そうした意図とは離れたところで強い印象を残すものがあった。
https://www.nact.jp/exhibition_special/2024/universalremote/
特に、地主麻衣子さんの映像作品は素晴らしかった。訴えられているメッセージが力強かったことはもとより、印象的なショットも多く、この作品観られただけでも来場した甲斐があったというものである。この方の他の作品も観てみたいと思う。
テクノロジー疎外論にいくことがいまいち腑に落ちない。AIがいくら絵や文章をかいたところで、「本物の」芸術と異なるのは自明なことで、情報に過ぎないことにアイデンティティをおびやかされるなら、その認知をもたらす構造に問題があるようにも思う。
2023年6月3日
昨夜は、眠いのになかなか寝付けなかったので、Le Petit Princeの朗読動画を見つけて音読したり、DELF A1の問題を解いたり、ちょうどよさそうな国際会議を調べたりしていた。さらに、西平直『稽古の思想』を読み始める。「稽古」という概念にこの数年関心がある。自分とは縁遠い言葉である。
途中目覚めたりしながら、11時過ぎまで寝ていた。8時間ぐらい寝ただろうか。久々。ややすっきり。
新宿へ出かける。操作ミスで『発音の教科書―日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの作り方がいちばんよくわかる』の音源が流れてきたのだが、いま一度聴いてみるといい感じであることに気づいたので、歩きながら聴く。通して聴き終わるまで、聴き続けてみよう。新宿について、紀伊國屋の地下のカレー屋さんで昼食。
紀伊國屋書店で、以下2冊を購入。
- 三野博司『「星の王子さま」で学ぶフランス語文法』
- 山口みどり他『論点・ジェンダー史学』
もうちょっと見てみわろうと思っていたのだが、時間があまりないのと、本を買い過ぎてしまうのを避けるために早めに出た。お茶しながら、本を読む。ここ最近追加したルーティンをまとめておいた。
- 『CDエクスプレス 古典ギリシア語』1章音読×1回
- Le Petit Prince音読1章×3回
- 『はじめてのDELF A1』回答・音読1章×1回
- 『表現パターンを身につけるフランス語作文』1章書き取り・音読×1回
- 聖書アプリ「ロバート・ロバーツ」1日分
- 『英語で読む高校世界史』音読1章×1回
新宿に来たのは「士業トップ×ITトップ 交流会」のため。パネルディスカッション2本に出るのであった(パネラーとモデレータをそれぞれ)。せっかくなので楽しんでもらえる感じにしたいということで、一緒の人が勢いがある人ばかりだったので、思い切り引き出す感じにしてみた。その後、懇親会。
ついつい文章をちゃんと書いてしまうので、もっと雑な感じで書いてみようと思う。どんどん取り払っていかないと。もっと気楽に、流れるままに書いていける感じに。
今日のブックマーク
- 2023 IEEE WFIoT IEEE 9th World Forum on Internet of Things | 12–27 October 2023 // Aveiro, Portugal
- Le petit prince - YouTube
- DELF A1 Practice - YouTube
- 超おもしろい古典制御の歴史。制御工学誕生のドラマとは!?
- [AはAであるさんはTwitterを使っています: 「この絵は重要だなあ。「日本」はこうなりそう。](https://t.co/dxpeuwoSHn」 / Twitter https://twitter.com/_tea_two/status/1664807142438887425)
- [藤村シシン🏛神話受容史講座さんはTwitterを使っています: 「#叙事詩さんぽ あさってです〜。 『イリアス』全部は読めそうにない人は 👉赤字の章を主に読む予定。ここだけでもcheck! 読む時間が3分しかない人は 👉冒頭7行だけ読もう、そこが要旨だ 読む時間がゼロ 👉ミリシラで戦場に来てOK、読書会後にゆっくり読もう](https://t.co/q1c9Cs6IfA https://t.co/zcBCXbAC4O」 / Twitter https://twitter.com/s_i_s_i_n/status/1664235625091043328)
- 中級アラビア語読本 宮本 雅行(著/文) - 鳥影社 | 版元ドットコム
- 作家の仕事部屋 ジャン=ルイ・ド・ランビュール(編集) - 中央公論新社 | 版元ドットコム
- GPUメモリが小さくてもパラメーター数が大きい言語モデルをトレーニング可能になる手法「QLoRA」が登場、一体どんな手法なのか? - GIGAZINE
- 「世界史」の世界史(学術俯瞰講義) The World History of “World History” (Global Focus on Knowledge) | UTokyo OCW (OpenCourseWare)
#日記 #6月3日
2022年6月3日
早朝に起きなければならないというのに、吉田修一『国宝(下)花道篇』に読み耽ってしまい、3時過ぎまで読んでいた。
朝8時から日本CTO協会の理事会。みんな忙しくて予定が合わないので、朝早い時間になってしまう。ワーキンググループの報告をしたり、決議事項やディスカッションなど。来月頭には理事らで箱根合宿の予定。そちらでまたいろいろ議論することになる。その後、ミーティングをいくつかした後、出社。面接など。
昨日、首こりについて書いていたら、Kさんが鍼灸を勧めてくださったので、意を決して予約を試みる。Kが通っている近所の病院。時間が合わなくて来週の木曜日になってしまったが、まずは一度行って見ないことには始まらない。しかし、首から肩がガチガチになっている現況をまずはなんとかしなければならないので、昨晩に引き続き、ストレッチを入念にする。
下高井戸シネマで、濱口竜介「偶然と想像」を観る。今日が最終日だったので、夕方から休みをとって観に来たのであった。この劇場に来るのは初めて。濱口監督の映画に頻繁に見出される、急速な展開によって人間関係が不可逆に変化してしまうシーンに、この映画ではさらに偶然性が合わさって、よりびっくりするような体験として提示される。よく練り上げられた流麗さは見事。3話目ではPASSIONから十数年後の二人がそろうということで、そういう意味でもグッとくるところがある。こちらは会話劇が主ということもあって、ハッとするようなロングショットは最後のシーンぐらい。そういう意味では少し物足りないが、単純に観ていて面白い。
その後、明大前に寄ってお茶しながら、下高井戸シネマで買った映画のパンフレット(普通のパンフレットと比べると、非常に豪華なもの)、NOBODY ISSUE 47、48をパラパラ眺める。この雑誌のことは全然知らなかったなあ。何をいままで見てきたのか、と反省する。もっといろんな情報が自動的に集まるような仕組みを作らないとなあとあらためて思う。フィードリーダを再構築しなければ。
そういえば、下高井戸から各駅の上り電車に乗ろうとして待っていると、3本電車が通過していって、ちょっと酷いんじゃないかと思ってしまった。また、明大前や、井の頭線の渋谷駅など、学生さんと思しき若者がたくさんいる光景に何年も触れていなかったので(そもそも京王電鉄の電車に乗るのが久々)、なんか20世紀に逆戻りしたみたいな気持ちになったりした(学生の頃は京王線沿線に住んでいた)。
ストリームの串カツ屋さんで会社の人々が飲んでいるという情報を得たので、勝手に参加。その後、恵比寿に移動してもう一杯やった後、帰宅。
2021年6月3日
「【速報!/ユーザー還元】早川書房の電子書籍1500点が50%OFF、夏のKindle本セール開催中!|Hayakawa Books & Magazines(β)」にある通り、早川書房からKindle本1,500冊が半額セールになっており、ひと通りみていった。その結果、10冊ほど購入。もうちょっとサイバーパンク的なものが出ていれば買ったのだけど。それでもまあ、先日の講談社祭りの時に何十冊買ったのかわからないぐらい買ったし、Kindle本がたまりにたまっているのだった(早川書房のも、買おうとクリックしたらすでに買っているものがいくつもあった)。
そんなわけで、これ以上積んでも……という気もするが、人生において積ん読が減るという状況がこれまで一度でも会っただろうか、いやない(読む速度より買う速度のほうが速いから)というわけで、気にせず買うしかないのであった。積ん読に対する意識は、普通のひとと我々(誰)とでは多分根本的に違っていて、我々(誰)の積ん読に対する意識(無意識)は、家にゴミをひたすら集めてゴミ屋敷をひたすら大きくしていかざるを得ないひと、みたいな感じで、なんらかの症状の発露という感じがする。読む・読まないに関わらず、買わずにはいられないという感じ。それでも自分などはまだだいぶマシなほうだろう。
田中克彦『ことばは国家を超える―日本語、ウラル・アルタイ語、ツラン主義』の続きを読み、読了。若い頃は青年文法学派的な信条が強かったという著者が、言語類型論のアプローチと、ウラル・アルタイ語やツラン主義の可能性を引き出すべく論を述べる本。印欧語族以外の「その他」的な扱いとしての、歴史的な周縁性みたいなところにはあまり実感はないのだが、ユーラシアの歴史を思うとそれも理解できる。また、単純にユーラシアへの憧憬みたいなのもあったりする。「祖語」のような架空概念よりも多様な言語の交通による「言語同盟」に起源を求めるビジョンはユーラシアの広い平原的であるし、確からしさも高いことであるとも思われた。
2020年6月3日
午前中仕事をこなしたあと、今週はなんかいろいろハードで疲れてきたので、Kが薬をとりにいくというのにつきあって近所を散歩。書店に寄って、『趣味と芸術 増補版 ―謎の割烹 味占郷』、「IMA(イマ)Vol.32 2020年5月29日発売号」、『芸術人類学講義 (ちくま新書)』、『ラディカル・ミュゼオロジー』、「暮しの手帖 5世紀6号」を買う。久々にアート関連の本を買ったなあ。最近書店にも行けてなかったせいで精神が乾ききっていたので、少しマシになった。その後、また仕事の続き。
面接などした後、夜は買ってきた本を読む。今号の「IMA」はスティーヴン・ギル。だいぶ巨匠をもってきたなあと、せっかく特集するならもっと若い人をしてほしいものだと思いつつ、やっぱり写真が良すぎて感銘を覚える。TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCHの小特集もいい。めちゃかっこいい。外に出ないから写真も撮れなくてそれはけっこうやなところなのだけど、こういうの観てるといいなあと思う。
さらに『趣味と芸術 増補版 ―謎の割烹 味占郷』。杉本博司さんが和食料理屋の主人として「貴賓」を軸と骨董と料理でもてなす連載というのだが、料理はどこかのプロの料理人(実はすごいひとだけど名前を隠している)が作っているのだろうと思っていたのだが(非常に品も見た目もいい料理なので)、途中でクレジットを確認したら料理人の名前がなく、本人が作ってるのか?この人はマジでなんなんだ???と思って、衝撃を受ける。もちろん、しつらえもヤバいのだが……。圧倒的に凄すぎる。ため息。あとこれはどうでもいいことなのだが、ゲストとして平野啓一郎さんと出ていた配偶者だというモデルの方が驚くほどの美人で、これまた衝撃を覚えた。
2019年6月3日
土曜日のトレーニングからの筋肉痛がかなりきつい感じ。
帰宅して、夕食を作って食べた後、M5Stackをいじったり、自分のホームページの改修をすすめたり。
このままではヤバいなという気持ちがある。自分的にもそうだし、世の中も全然違う状況へ変わっていく予兆。焦燥を感じてもしかたがないので、いい機会にしていかないとなあ。
この10数年ぐらい、自分は10年ぐらいひとからいろんなことが遅れているという気がしている。社会的な位置付けもそうだし、考え方も幼いという気がする。逆に、だからこそのびしろが大きくて、ある意味ではそのために相対的に成長率が高かったということなんだろうと思う。そして、そののびしろを食い切ってしまったあとに、どうしていくべきなのかという問題が今後起こるのだろうと思える。
2018年6月3日
京都で撮ったものから画像を作る。いくつか、以下に貼る(あとはアルバムに)。




たとえば、いまの職務についているのがもし自分でなければ、すなわち、他の誰かであったとしたらなにかもっとうまくいくのだろうかと、具体的に何名かの顔を思い出しながら考えてみる。どうだろうなあ。
『狂うひと ──「死の棘」の妻・島尾ミホ』の続きを読む。
2017年6月3日
家でダラダラしていたのだが、自転車で出かける。
原宿のNew Era Tokyoで買い物。
その後、都営新宿線の上あたりをふらふらしながら、飯田橋の、神田川が外濠と接続するあたりをじっくり検分した。以前から、具体的にどういう風につながっているのか気になっていたので。
三崎町のうつわ千鳥へ。初めていったのだが、随分と古いビルに入っていて驚く。いいものはあるのだが、ピンとこなくて、何も買わずに出る。そこから、北の丸公園をぷらぷらした後、半蔵門から新宿通りを四谷方面へ。
迎賓館から赤坂御所の道を通り、神宮外苑を抜けて、神宮前から代々木公園へという道が、走りやすいし緑が多いしで、最高のルートであることを発見した。うれしい。気持ちがいい。
丸善ジュンク堂書店で、「東京かわら版」、『その後の慶喜: 大正まで生きた将軍 (ちくま文庫)』、『東大生クイズ王・伊沢拓司の軌跡 I 頂点を極めた思考法 (QUIZ JAPAN全書)』を買う。帰宅して、クイズ本を早速読み始める。非常に面白い。
2016年6月3日
体幹トレーニングとかしたらよいのではないだろうかと思い始める。なんかこう、踏ん張りがきかないというか、バランスを崩すことが多い気がするし。しかし、ググってみても宣伝ばかりで、どこがいいのかさっぱりわからないな。誰かがおすすめしてくれるところに行くのが一番よさそう。
そういうことはよくあって、最近でいうと、電子工作をやってみようと思ったのだが、道具をそろえたりするのが面倒で、なんかもう、詳しいひとと秋葉原にいってそのひとがいうままに必要な物をかごに入れてひたすら買うというのが一番早いと思い、そうすることにした。
単純に脳が古くなってきて新しいことになかなか取り組めないということもあるし、とはいえ自分が好きなことについてはふつうにいちから取り組めるのであるから、単純にまだそれほど好きなわけではないということもあり得る。また、あれこれを考える必要があるために思考法を最適化していて、そのせいで無駄に大量の情報量を扱わなければならなくなってしまっているということもあるだろう。
脳のスペックの高低はしかたがないが、考え方のモードを増やしたり、それらをうまく調整したりすることで少しはなんとかなる面もあるはずで、自分のいまのモードを自覚して、適切なモードを選択することで、そうした問題は乗り越え可能なことが多いように思える。